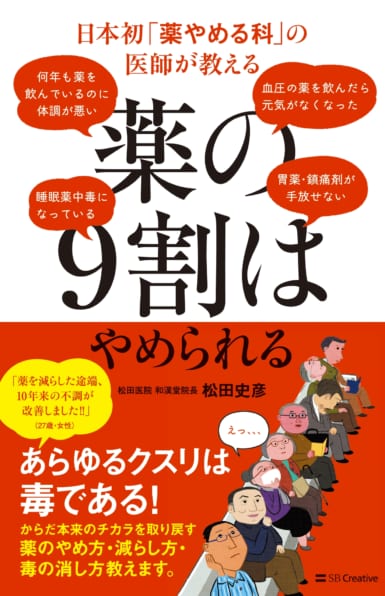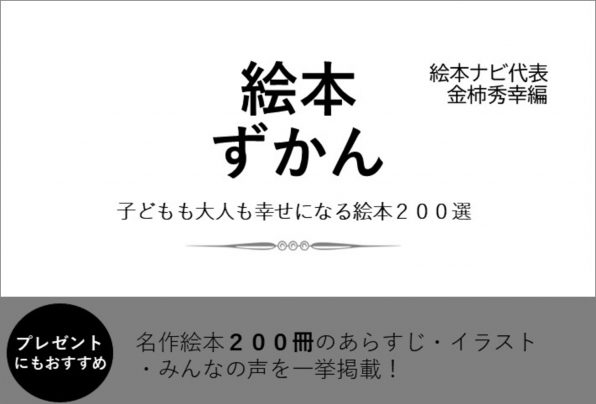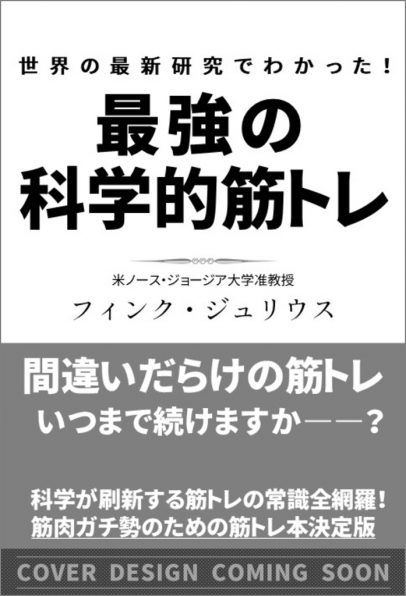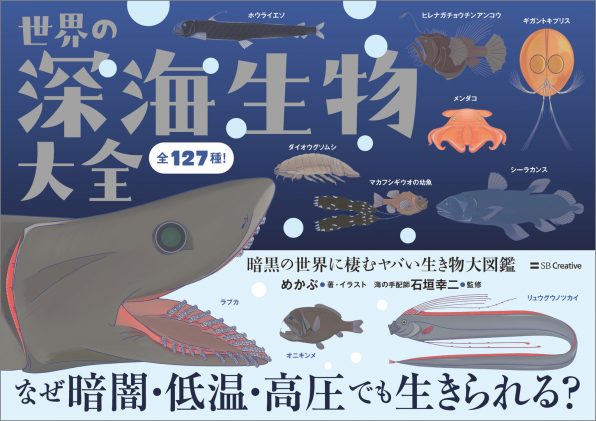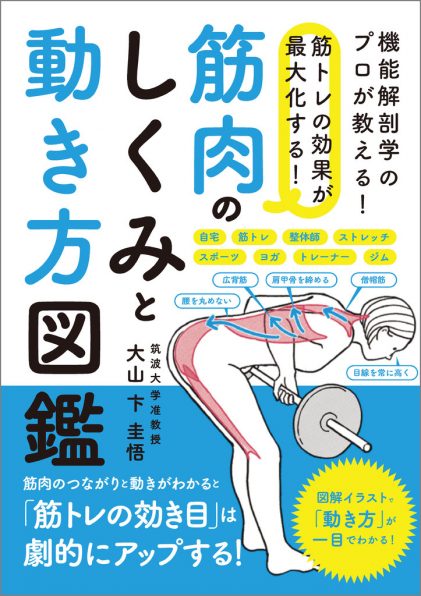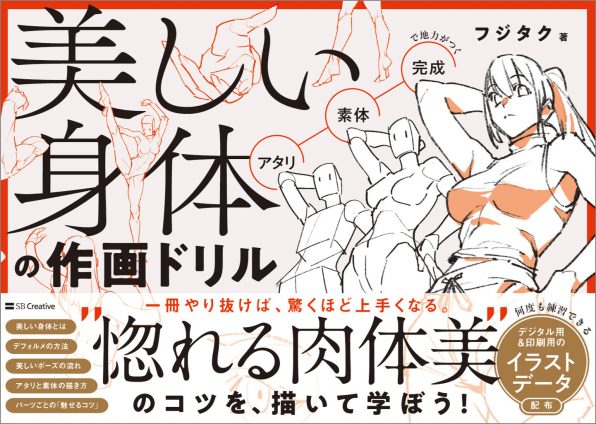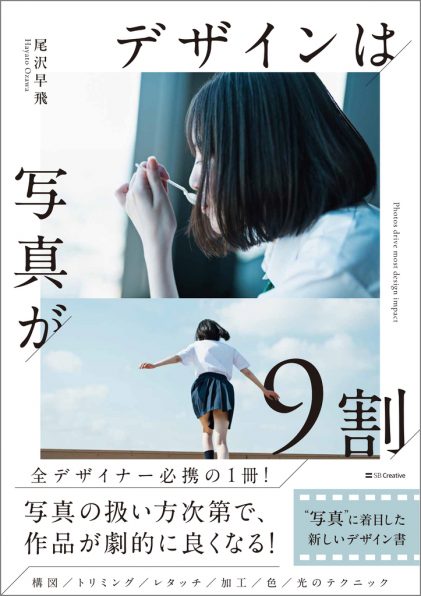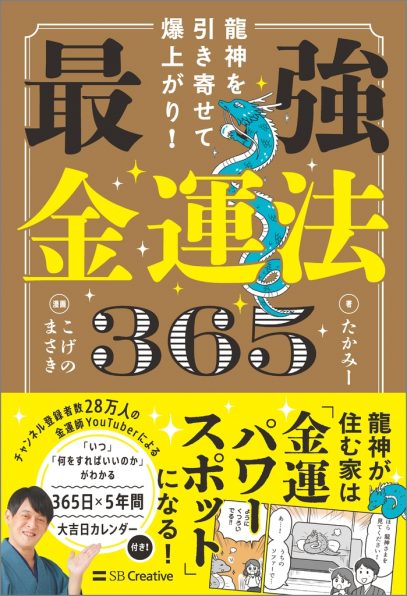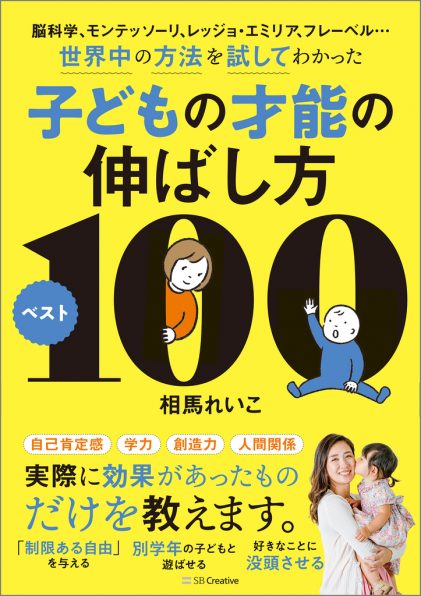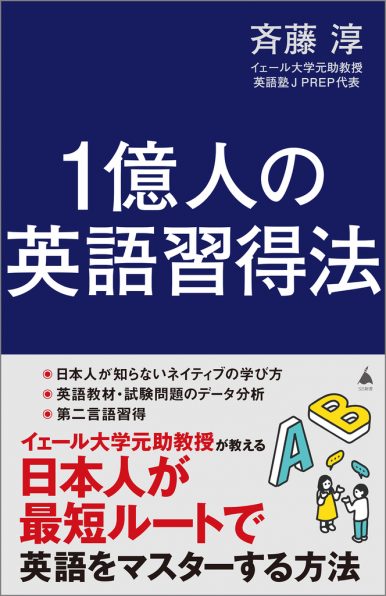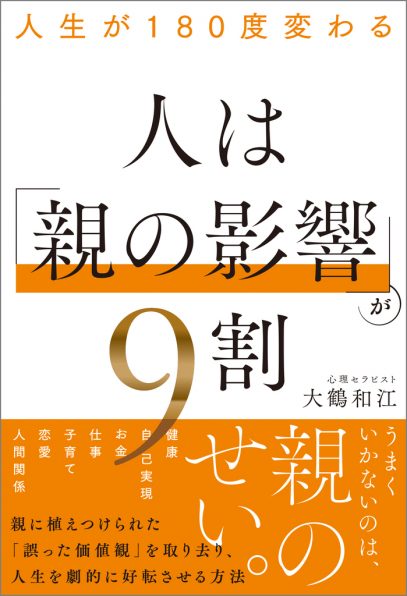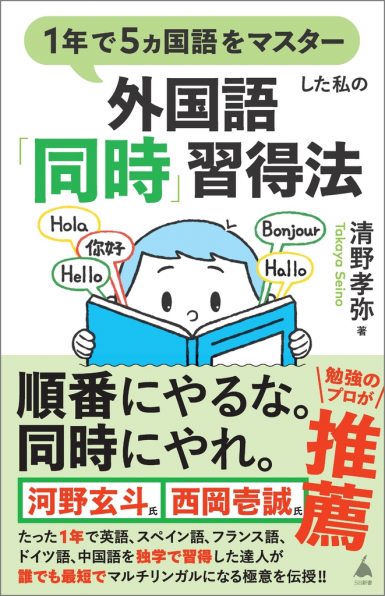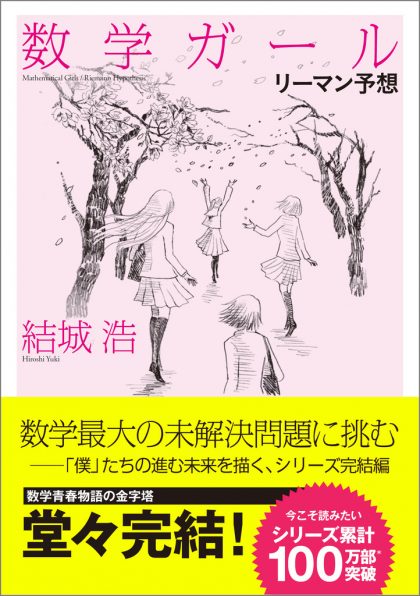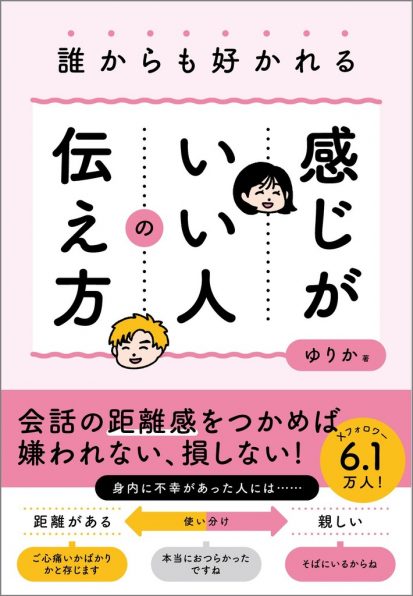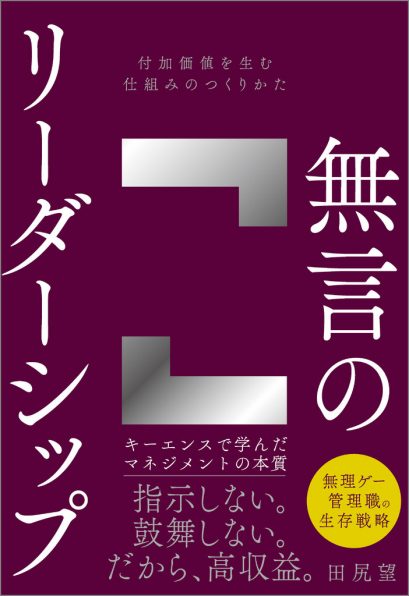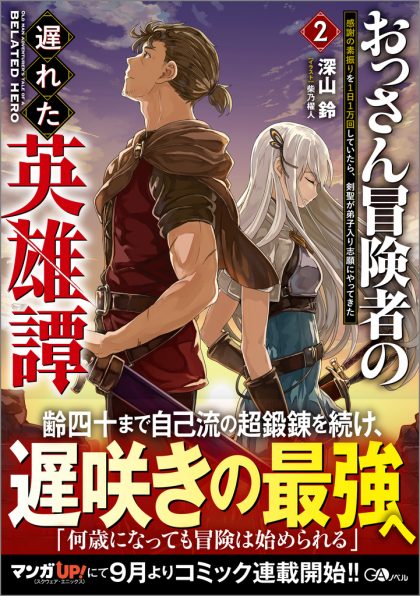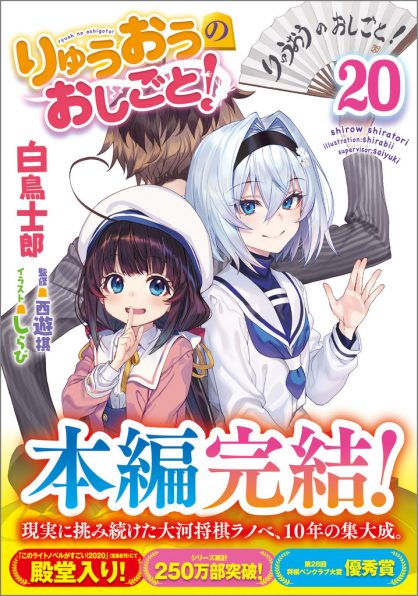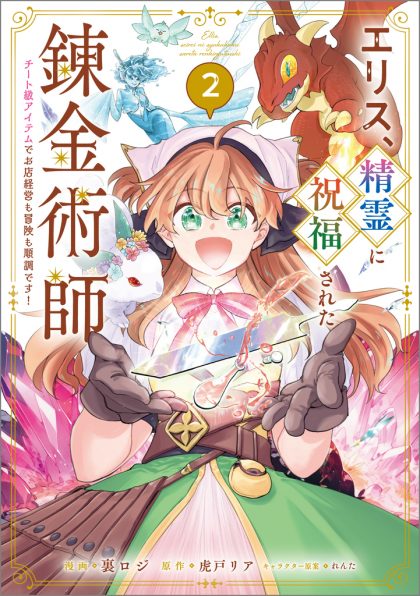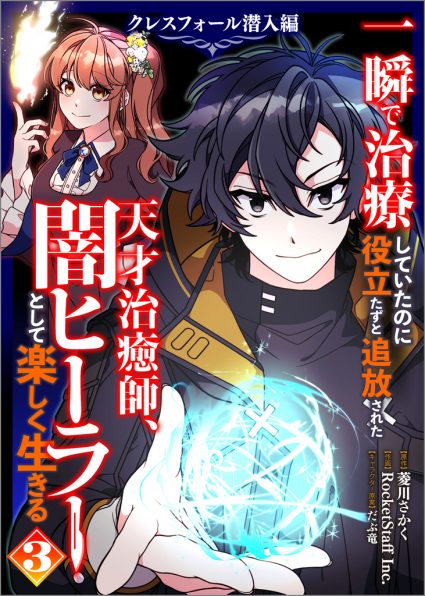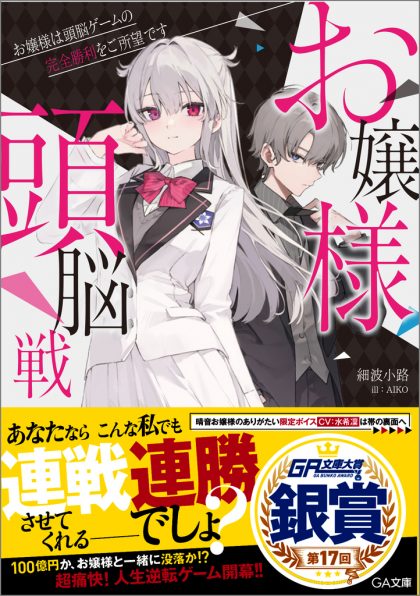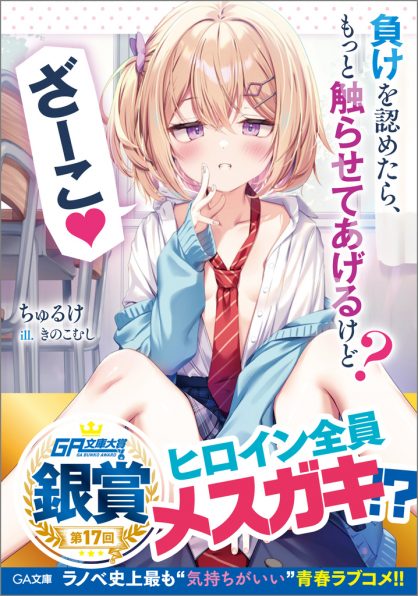日本初「薬やめる科」の医師が教える 薬の9割はやめられる
長年薬を飲み続けているあなた。このまま薬漬けで本当にいいの?
日本初「薬やめる科」を開設した医師が教える、薬のやめどき、減らし方、やめ方、溜まった毒の消し方。
薬に頼らず、本当の健康を手に入れるための本!!
「薬漬け医療」と言われて久しい日本の医療
。高齢になるほどに、目を覆うばかりの多くの薬を、長期間にわたって出し続ける傾向にあるようですが、死ぬまで投薬する意味が本当にあるのでしょうか?
日本初の「薬やめる科」を設けた松田医院和漢堂院長の松田先生は「多くの医師達は薬が基本的に毒であることを忘れている」、と指摘します。
特に問題となるケースは3つ。
1)高齢者が複数の科から大量の投薬を受けている場合、
2)心療内科、精神科などで数多くの精神安定剤を長期に投与されている場合、
3)繰り返す蕁麻疹、湿疹、アレルギー性鼻炎、喘息等に対して、抗アレルギー薬、ステロイドを長期連用している場合など。
少し周りを見渡せば、このようなケースはたくさん思い当たると思います。
このような状況を少しでも改善するため、松田先生は、「薬やめる科(減薬・断薬サポート)」を開設し、医者が絶対に教えてくれない薬のやめどき、減らし方、やめ方、溜まった毒の消し方をお教えします。
現場で多くの患者を診てきた医師だからこそわかる、断薬の大切さと効果。
長年薬を飲み続けているにもかかわらず、体調不良を抱え続けている人たちへ、「このまま薬漬けで本当に良いのか」を問う本です。
■目次:
はじめに――薬と体調、負の連鎖に歯止めを!
1章 薬が病気をつくる
2章 その薬はいますぐやめられる
3章 減薬から断薬へ
4章 抗精神薬・睡眠薬の恐怖
5章 「薬をやめる科」の挑戦
6章 薬いらずの暮らし方
7章 医療の現実と今後に向けての提言