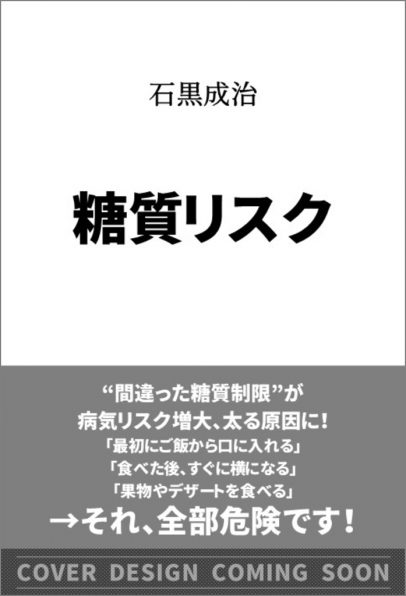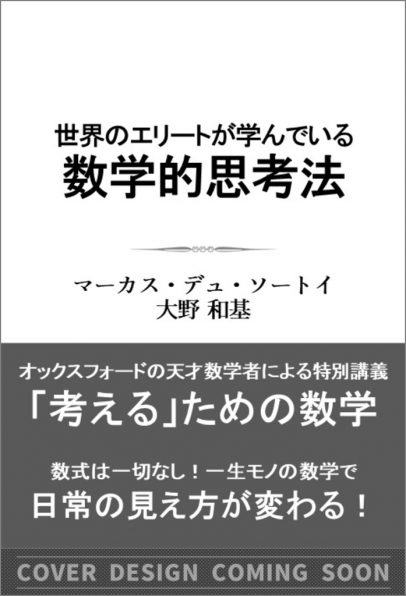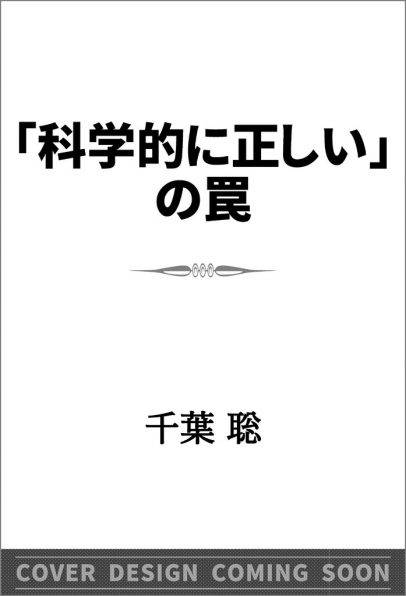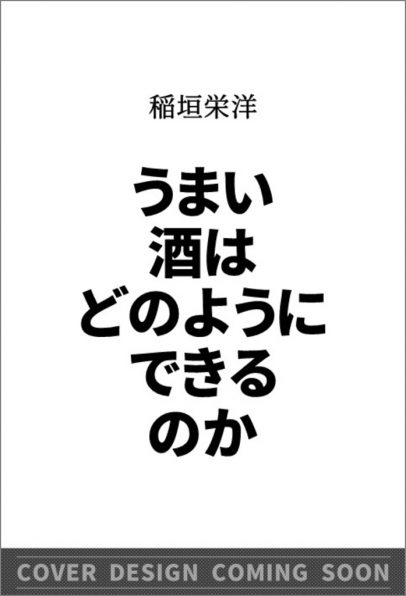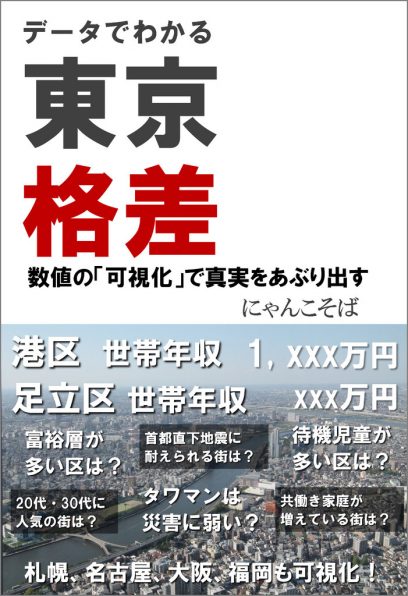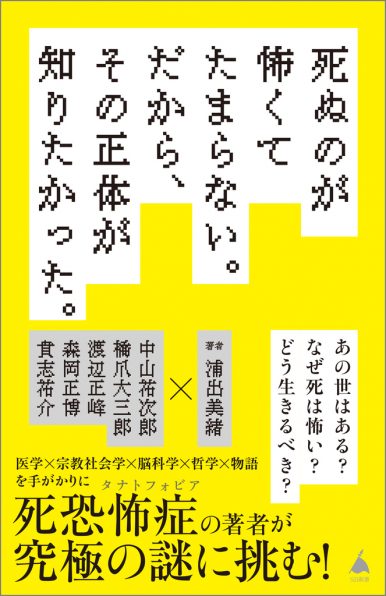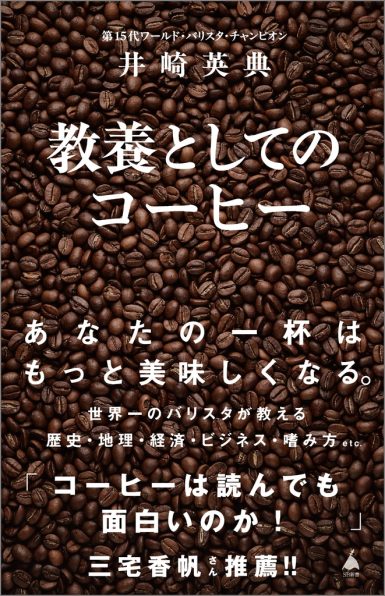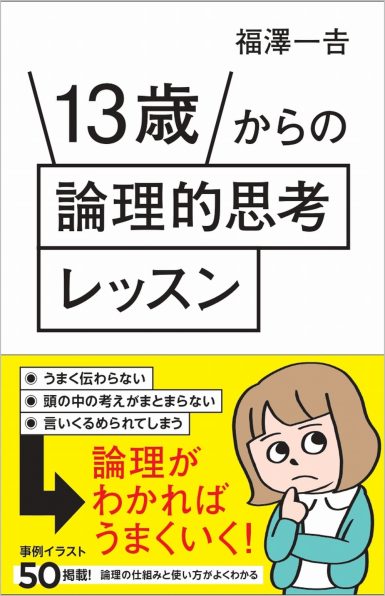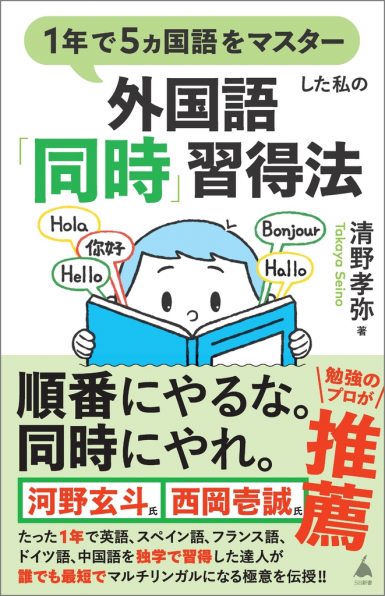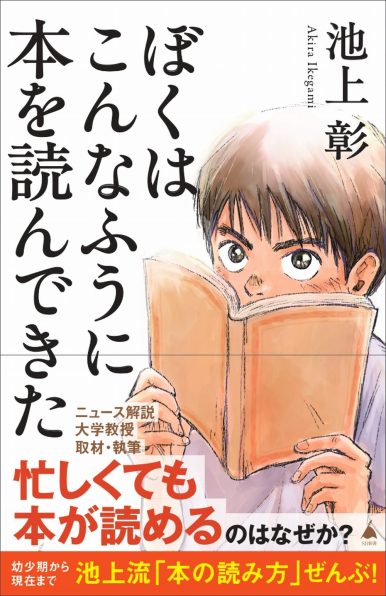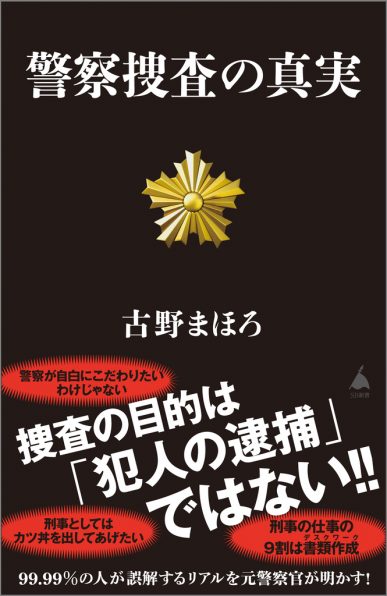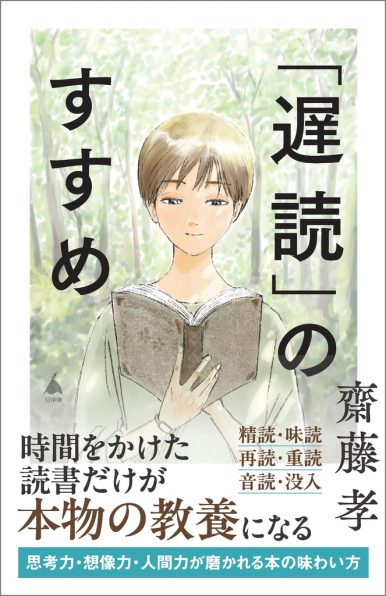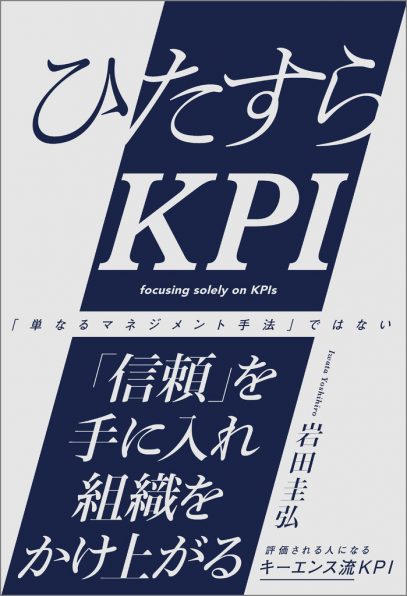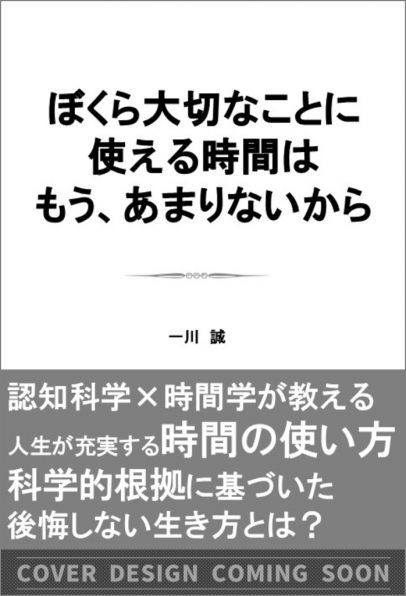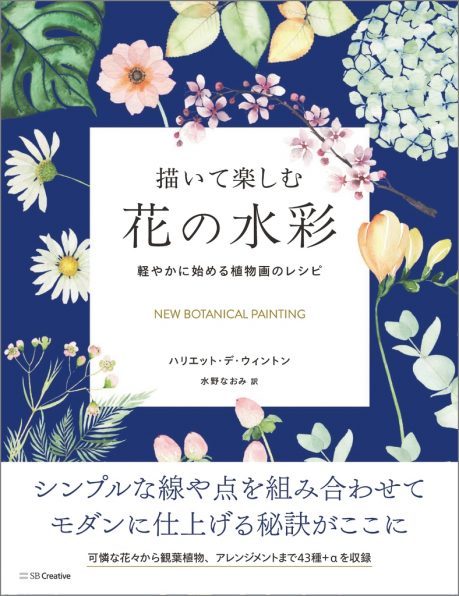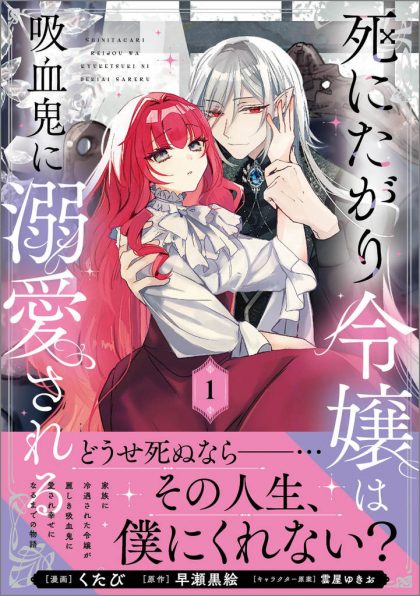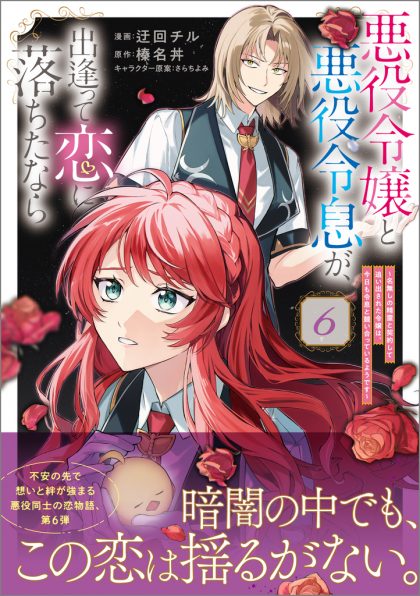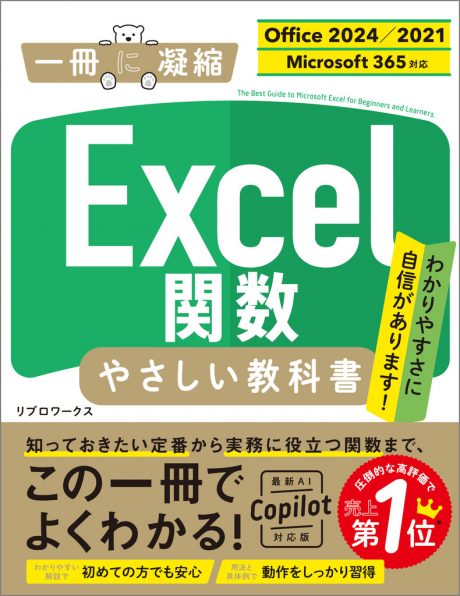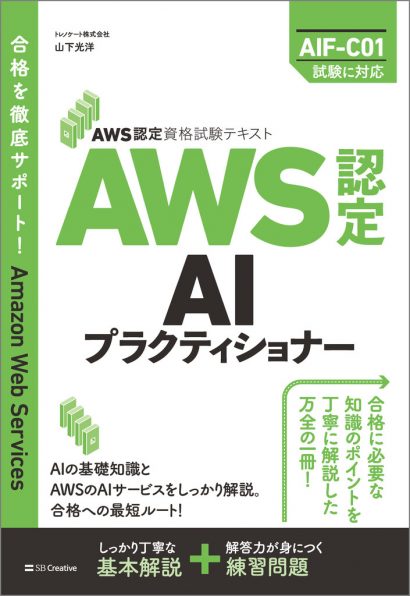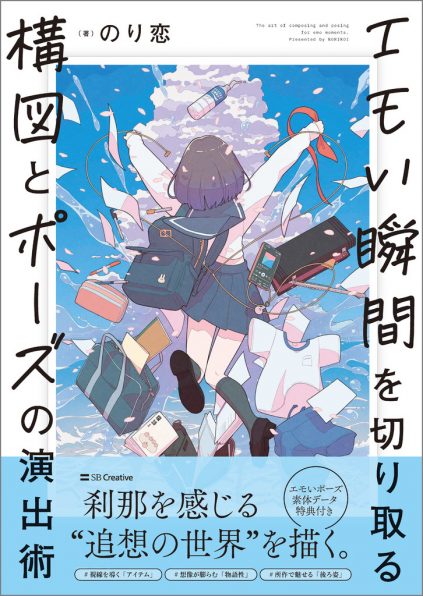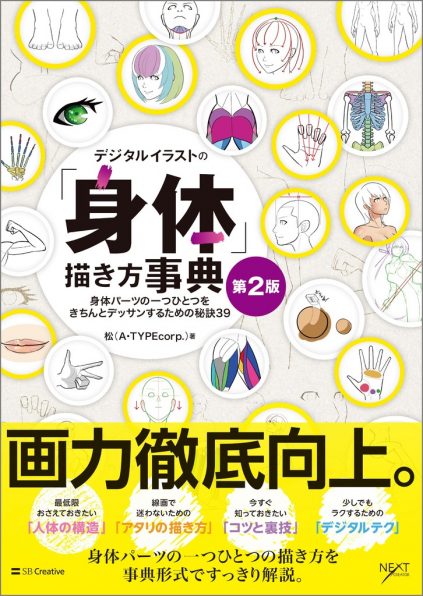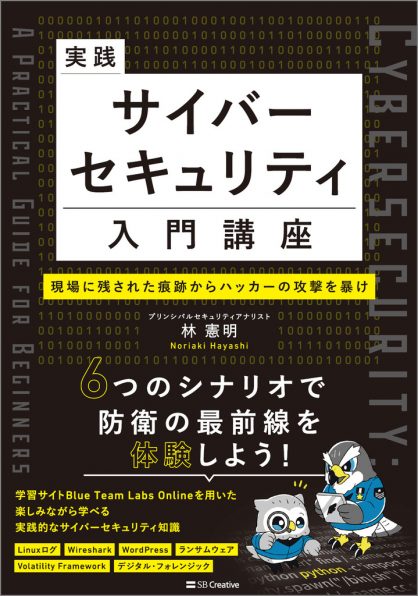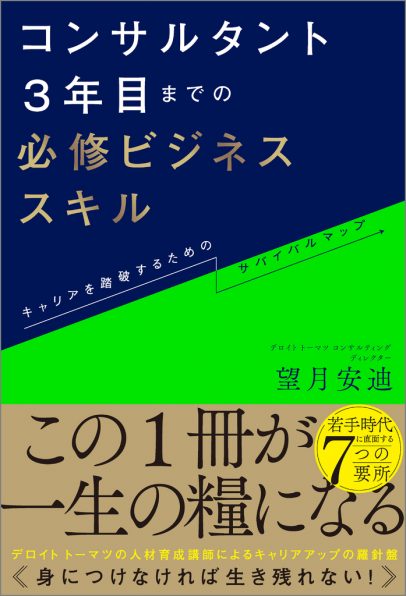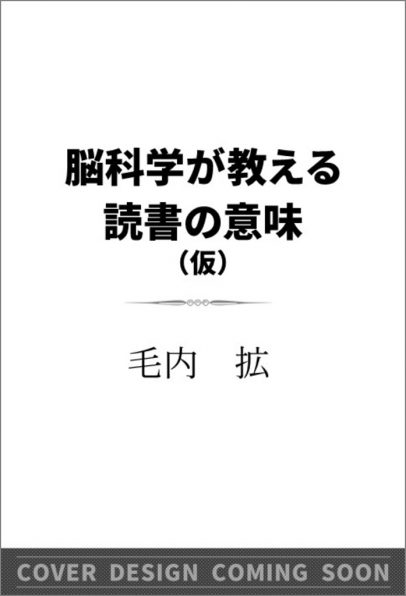
脳科学が教える 読書の意味
読者は、もう一人の著者である。脳科学が解き明かす「本を創る」読書術
最新の脳科学の知見から、読書が私たちの脳にもたらす効能と、効果的な読書術を解き明かす!
情報過多とデジタル化の波によって、私たちの脳は常に疲弊しています。
そして、「深く考える」時間と能力を失いつつあります。
本書は、そんな時代に読書が脳にもたらすさまざまな効能を、科学的かつ具体的に解説します。
▼セールスポイント
・科学的裏付け:読書中に脳内で何が起きているのかが分かる
読書中、脳のどこがどう働くのかを分かりやすく解説し、「なぜ本を読むと頭がよくなるのか?」を科学的に解説する。また、頭の良さだけでなく、読書が心の健康や共感力、創造性をも向上させる理由を明らかにする。
紙の本or電子書籍、黙読or音読など、読書スタイルごとの脳の違いについても分かる。
・脳の仕組み的に効果抜群の「最強の読書法」を紹介
脳科学に基づいた、「快読・精読・音読」の使い分けを解説。
また、ちょっとした工夫で、誰でも読書習慣が続くようになる秘訣も紹介する。
▼本書で解説している、読書と脳についての謎
・なぜ「紙の本」で読んだ内容は記憶に残りやすいのか?
・わずか6分間の読書がストレスを68%も軽減する、驚異的なメカニズムとは?
・読書によって「頭が良くなる」のはなぜか?
・漢字と仮名が混ざった文章を、脳はどうやって理解しているのか?
・読書中に、内容と関係のないことを考えてしまうのはなぜか?
・「快読」「精読」「音読」の科学的な使い分けとは?
・読書のモチベーションを上げる科学的な方法とは? など多数。
「読書の価値を今一度見つめなおそう」というブームの中で、必読の一冊です。
読書には二種類ある。
一つは、流行や他者の評価に流されて、内容をなぞるだけの「消費する読書」。
もう一つは、自分自身の思考や感性を働かせ、新たな価値を創り出す「創造する読書」。
実はこの「創造する読書」こそが、情報過多で疲れ果てた私たちの脳を癒し、そして鍛えるための大きな鍵なのだ。
本書では、読書が私たちの脳にもたらす効能と、効果的な読書術を、最新の脳科学の知見から解き明かしていく。
▼本書で解説する、読書と脳の謎
・なぜ「紙の本」で読んだ内容は記憶に残りやすいのか?
・わずか6分間の読書がストレスを68%も軽減する、驚異的なメカニズムとは?
・読書によって「頭が良くなる」のはなぜか?
・漢字と仮名が混ざった文章を、脳はどうやって理解しているのか?
・自分に都合のいい情報しか見ない「認知バイアス」はなぜ起こるのか?
・読書中に、内容と関係のないことを考えてしまってもよいのか?
・「快読」「精読」「音読」の科学的な使い分けとは?
・読書のモチベーションを上げる科学的な方法とは?
など多数。
はじめに――読者が本を作っている
第1章 読書の現状と課題:脳科学から見た現代の読書習慣
・子どもたちの読書習慣の衝撃的な現状
・読書習慣の「二極化」――読書時間「平均3分減少」の背後にある構造的問題
・子ども時代の読書経験がもたらす長期的な影響
・文化庁調査が示す読書習慣の変化と課題
・社会人における読書のデジタルシフトとコロナ禍の影響
・読書の価値は「冊数」では測れない――大切なのは「深く丁寧に読むこと」
・「読書時間の質」が重要
・デジタル時代における紙の読書の再評価と重要性
・音声・動画コンテンツへの移行と読書習慣への影響
・紙媒体からデジタルへの移行が脳の認知プロセスに与える影響
・読書媒体の違いが認知機能に与える影響
・紙媒体とデジタル媒体における読解力・記憶力の比較
・デジタルメディアがもたらす情報消費行動の変化と認知能力への影響
第2章 読書がもたらす脳科学的メリット
・脳が常に新しい刺激を求めてしまう理由とは?
・情報過多が脳疲労を引き起こすメカニズムとその弊害
・ヒューリスティックが引き起こす「認知バイアス」の問題
・デフォルトモードネットワーク(DMN)と反芻思考
・読書がもたらす脳と身体のリラックス効果
・なぜ読書は脳や心の「休息」になるのか
・読書中の「心のさまよい」は悪いことではない?
・読書による「頭が良くなる」脳科学的メカニズム
・読書と認知症予防――脳の長期的な健康への貢献
第3章 文字と言語処理の脳メカニズム
・漢字――書けないけど「読めちゃう」の不思議
・文字の誕生と発展の歴史
・表意文字(漢字)の脳内処理
・表音文字(アルファベット、ひらがな、カタカナ)の脳内処理
・日本語――表意文字と表音文字が混在する特殊な言語
・日本語が読めるのに読書しないなんてもったいない!
・話し言葉としての日本語
・日本語は想像力のレーニングになっている
・耳から聞く読書(オーディオブックなど)はどうなのか?
・字幕付き動画はどうなのか
・映画はもはや情報過多?
・映画・動画とは異なる読書体験の正体
第4章 認知バイアスとセルフトークによる自己調整
・自分に都合のいい情報しか取り込まない認知バイアス
・脳の数だけ現実がある
・知恵ブクロ記憶とは何か?
・ワーキングメモリの役割
・スキーマの構築と調整
・柔らかい脳のはたらきを支える「シナプス可塑性」
・読書中のセルフトークに着目してみよう
・ネガティブなセルフトークはどうか?
・読書体験によって得られる「精神的自由」
・本章のまとめと今後の課題
第5章 効果的な読書技術とアウトプット
・快読・精読・音読──目的に応じた使い分け
・快読(飛ばし読み)の脳メカニズムと活用法
・精読の脳メカニズムと活用法
・どちらが優れているというわけではない
・行間を読むとはどういうことか
・音読の脳メカニズムと活用法
・アウトプットの重要性と定着メカニズム
・読書習慣化のための実践的方法
・「クエスチョン立て」の実践
・「読書カード(メモ)」の実践
・その他の実践的Tips
・小学校の読書感想文カリキュラムに学ぶ大人向け実践法
第6章 読書が育む共感と社会性
・読書は「著者とのコミュニケーション」──ミラーニューロンと代理体験
・集団協力・社会的適応を支える共感能力の進化的役割
・「精神的自由」を行使していると言えるのか
・読書を通じて広がる「精神的自由」
・情報過多と脳疲労からの解放
・未来への展望と創造性の涵養
コラム① 本で死にかけた?
コラム② 読書週間をとり戻す取り組み
コラム③ 本に生かされた
コラム④ おもしろい本の選び方
コラム⑤ 書評の企画――『週刊現代』リレー読書日記の経験から
コラム⑥ いんすぴ!ゼミ
参考文献
ブックガイド