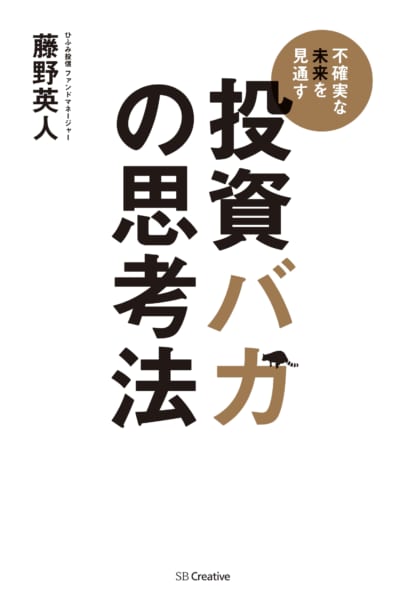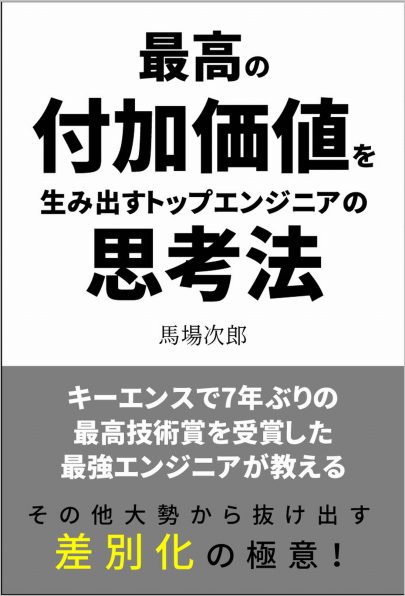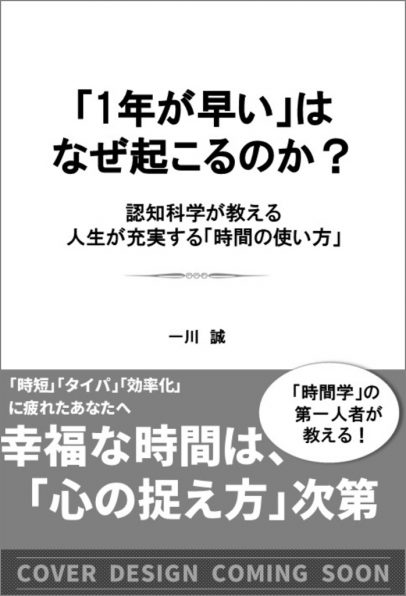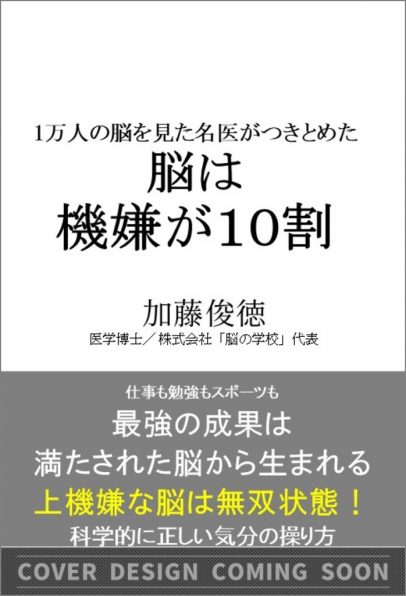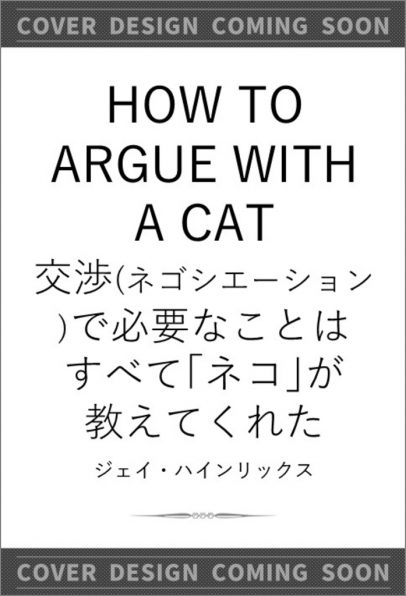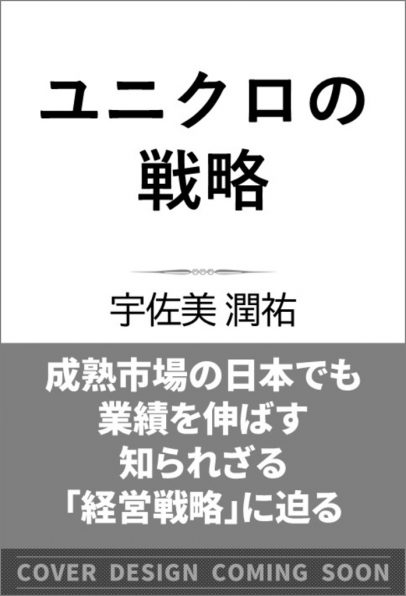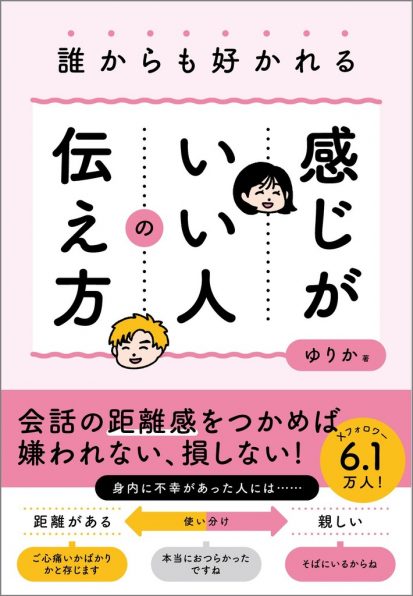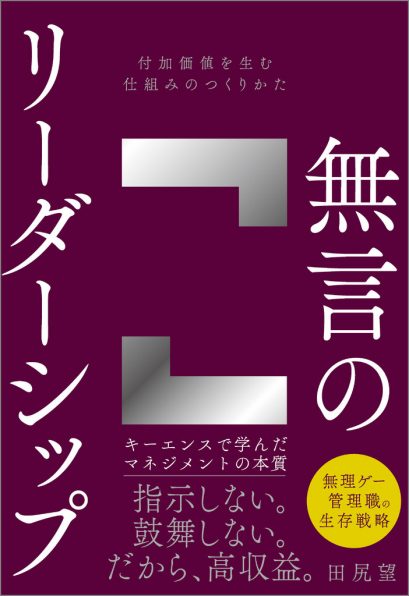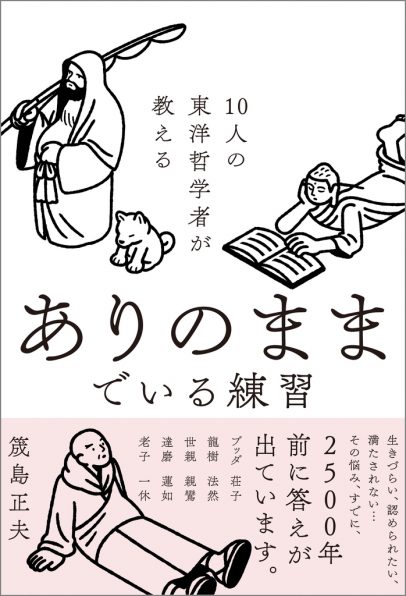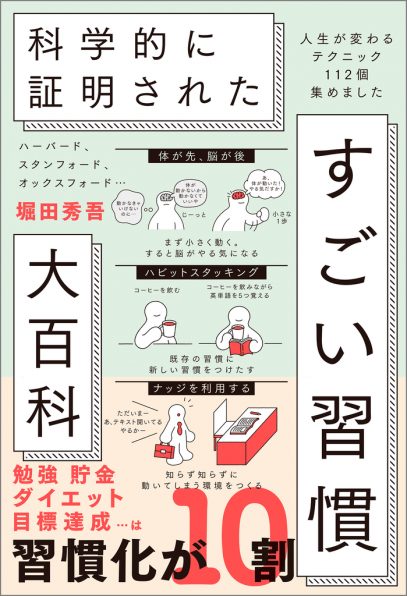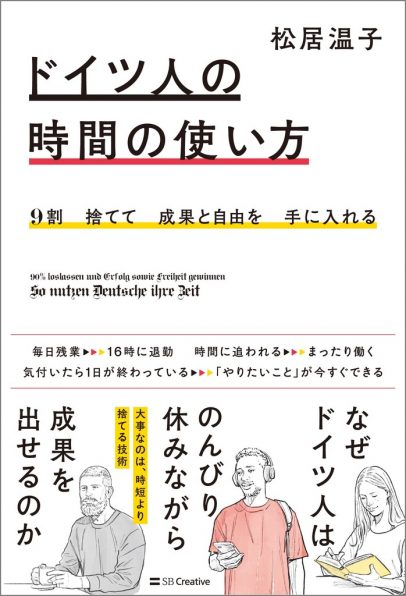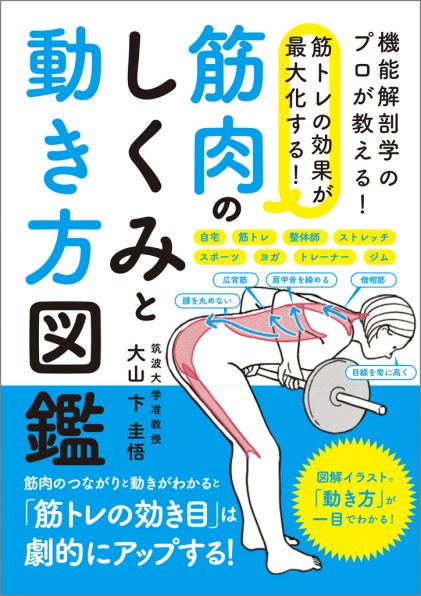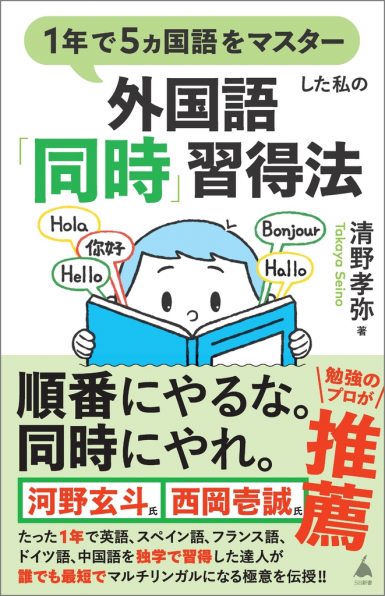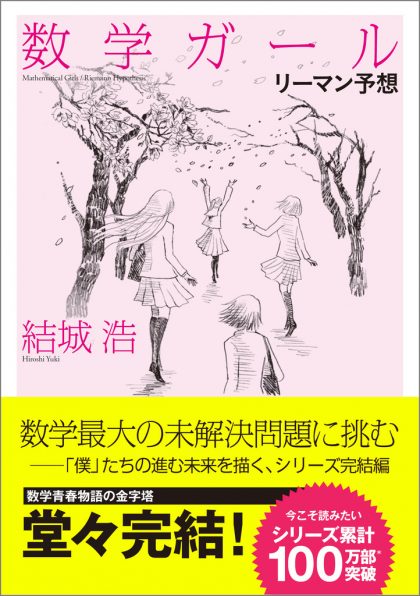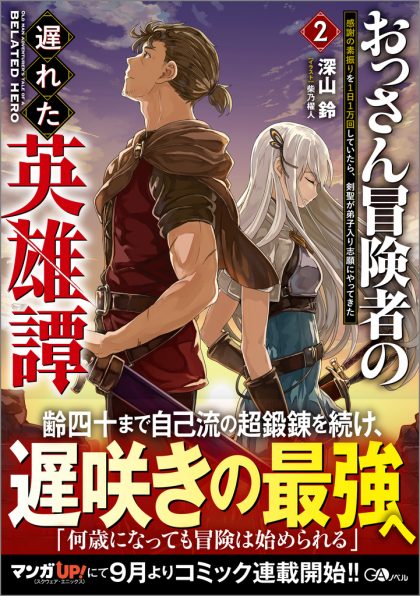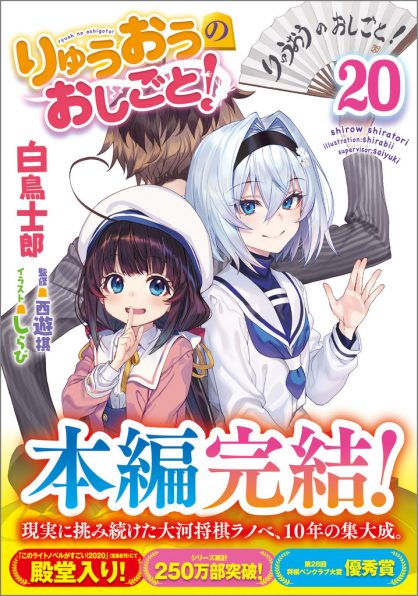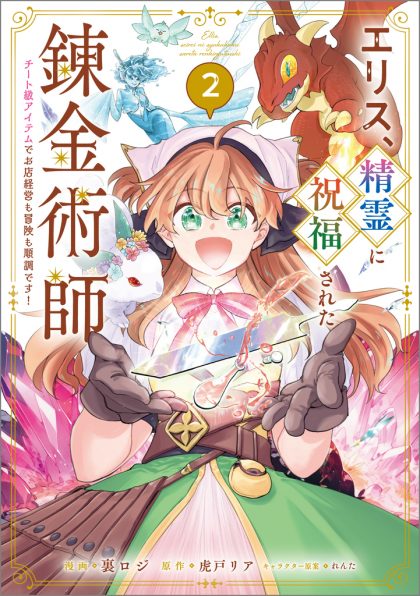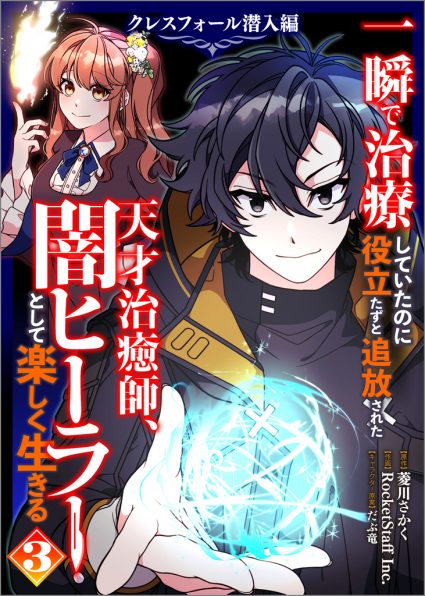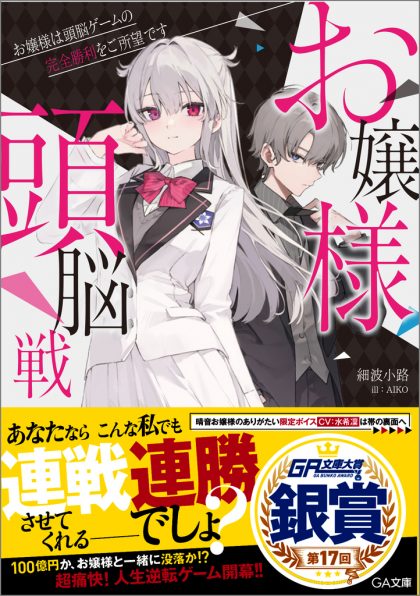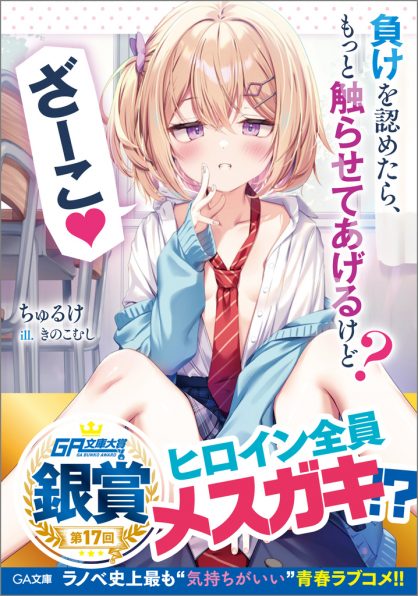投資バカの思考法
◆先が見えなくても、前に進む力をつけよう!
4年連連続ファンド大賞を獲得の投資家が教える、先の見えない時代を生き抜く思考法
R&Iファンド大賞4年連続受賞!
「結果を出し続けてきた」投資家の投資哲学!
「本書は、私がこれまで25年間で磨き上げてきた、
投資のプロとしての経験と知見、メソッドを
一冊に凝縮したものです。
『投資』と『お金』の考えをすべて詰め込みました」
著者の藤野英人氏は、「ひふみ投信」のファンドマネジャーとして、
R&Iファンド大賞を4年連続で受賞、
デフレやリーマンショック、東日本大震災など、どんな経済状況でも、
25年以上実績を出し続け、「カリスマ投資家」と呼ばれている。
著者は、「投資とは、日経平均を予測するギャンブルではない。
未来が予測できなくても、長期的には勝ち続けることは不可能ではない」という。
なぜ、激動の時代でも勝ち続けることができたのか。
その方法を、すべて明かしたのが本書である。
■目次:
序章 そもそも、「投資」とは何なのか?
第1章 洞察力 ―マーケット感覚を身につけたいなら、街を歩け―
第2章 決断 ―決断とは、やらないことを捨てること―
第3章 リスクマネジメント―リスクの分散とは「好奇心」の分散である―
第4章 損切り ―評価は常に「時価」で考える
第5章 時間力 ―「お金」、「効率」よりも大切なもの―
第6章 稼ぐ力 -「お金」と「経済」の本質をつかむー
第7章 選択力 ―未来に向けて、希望を最大化する戦略―