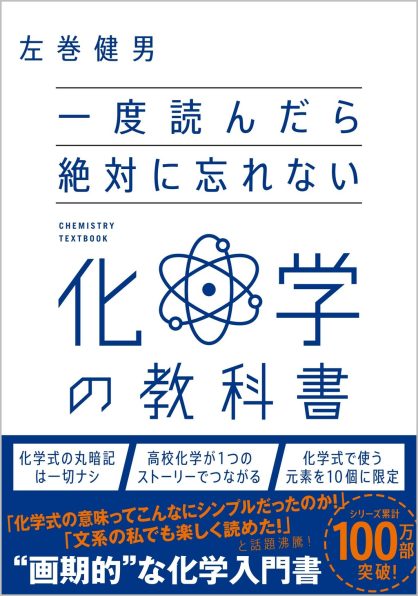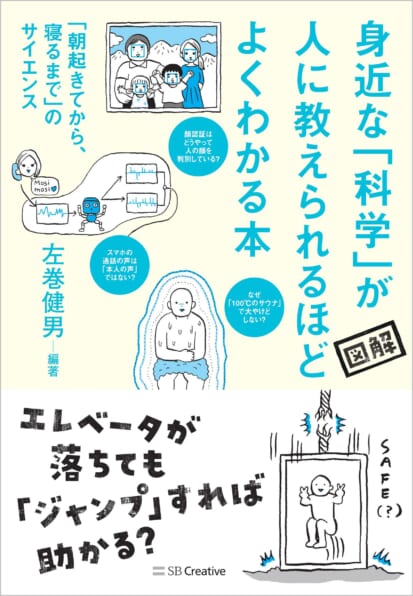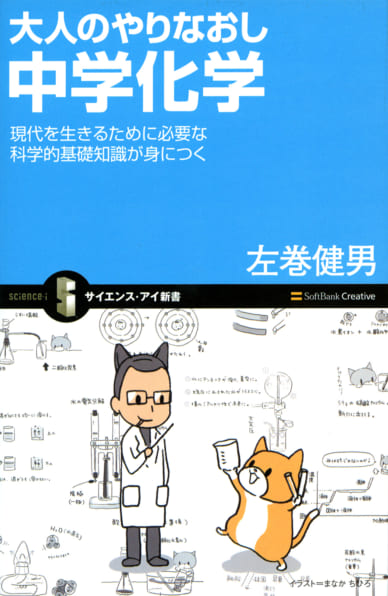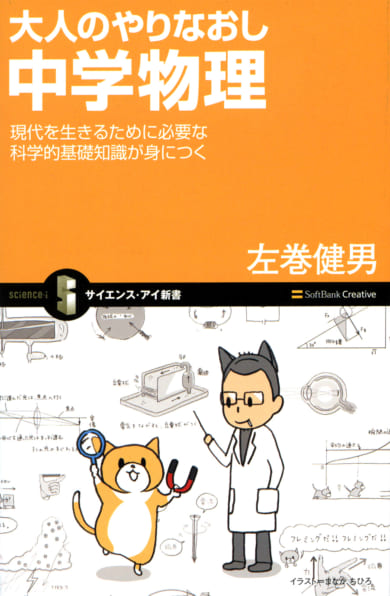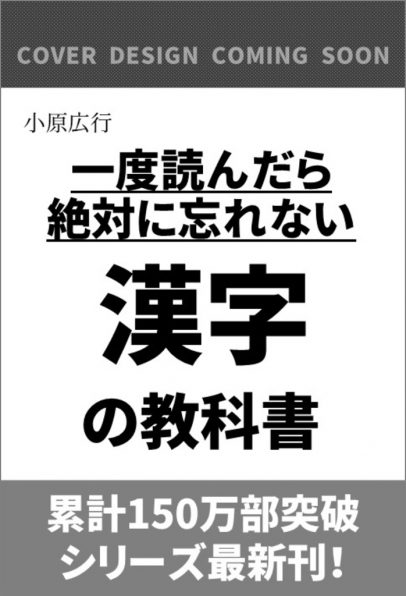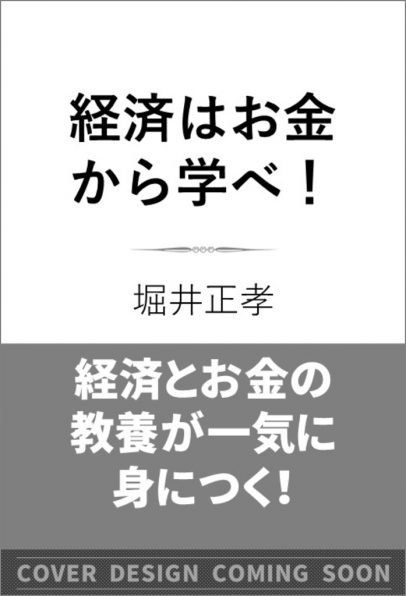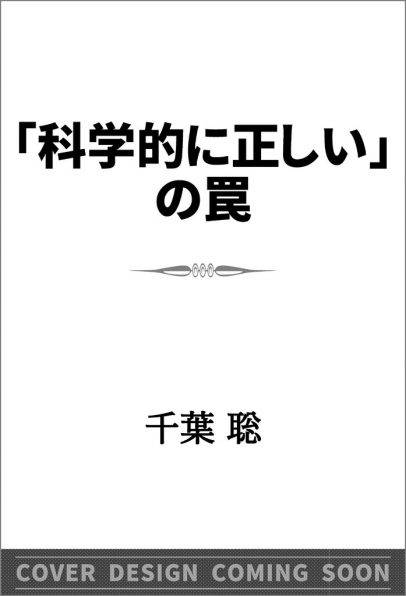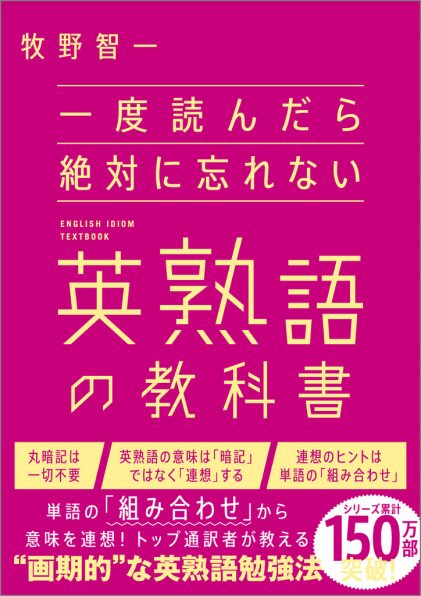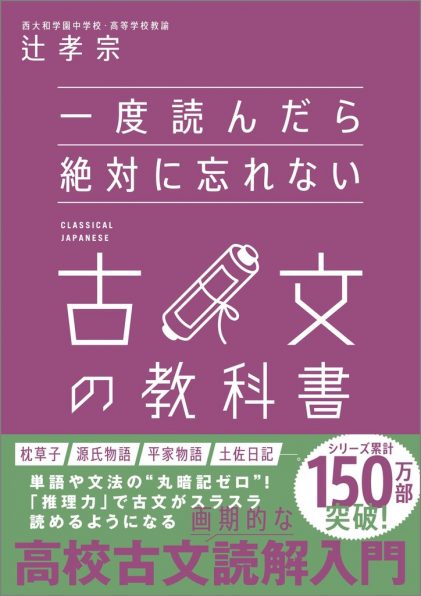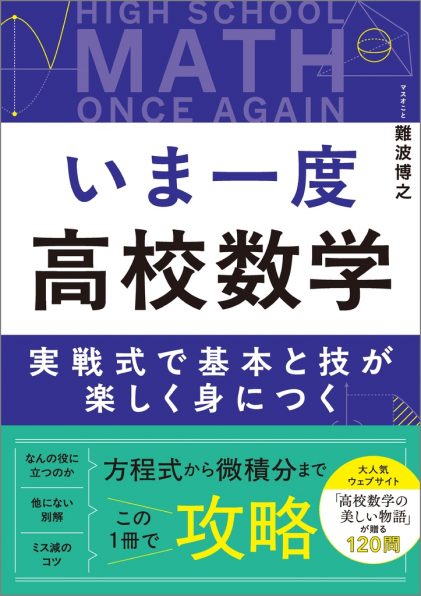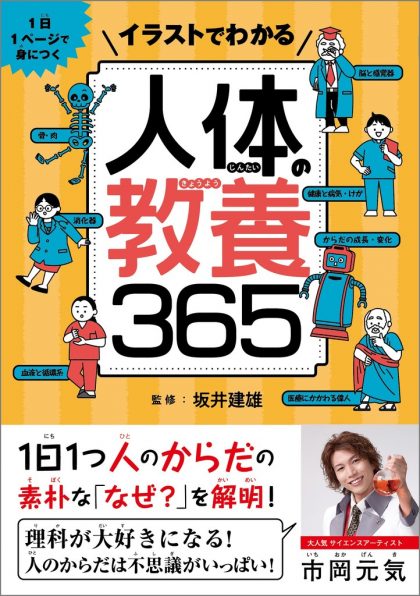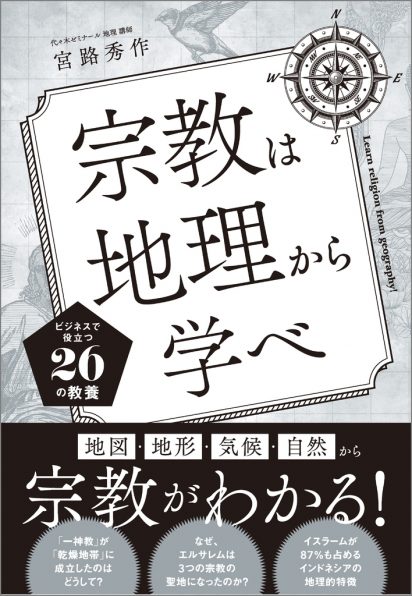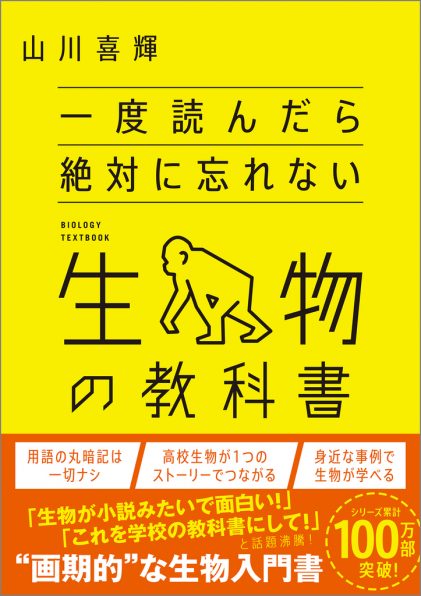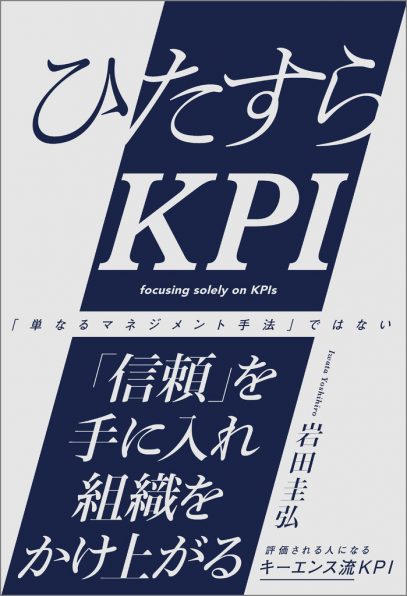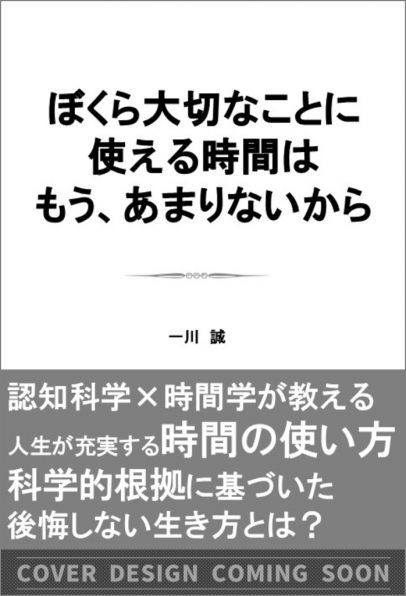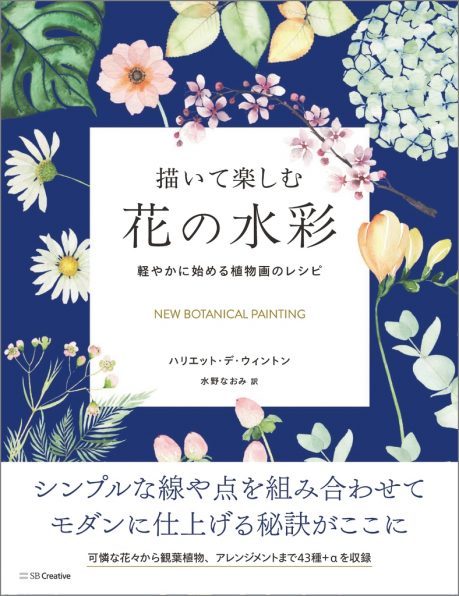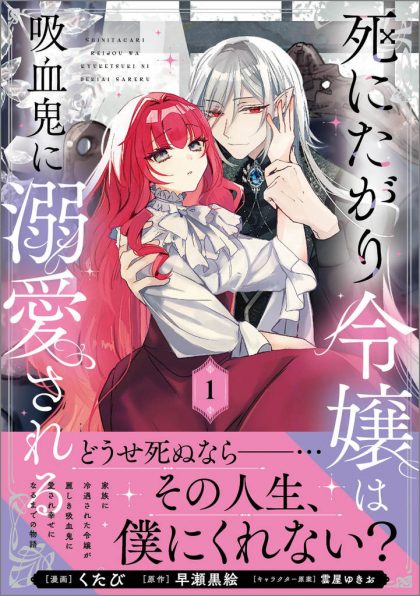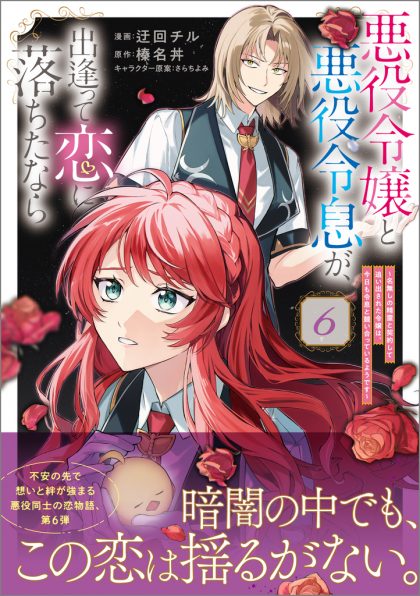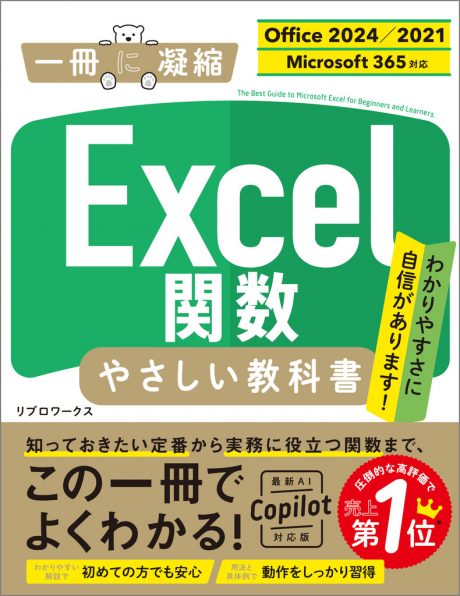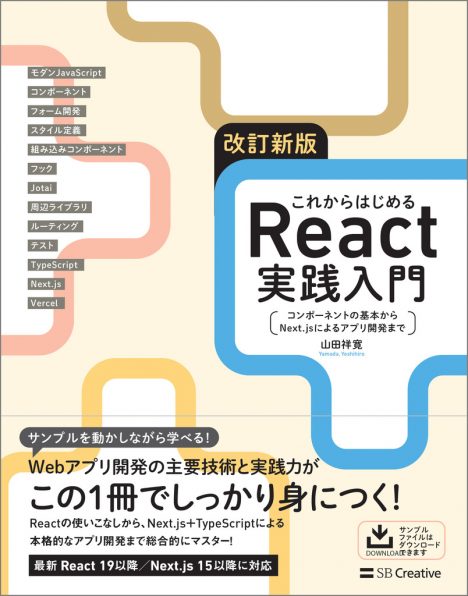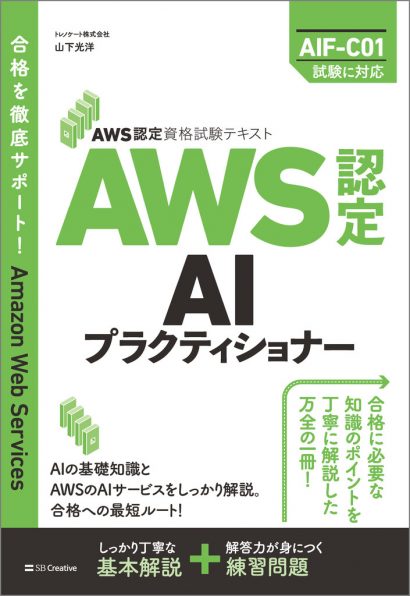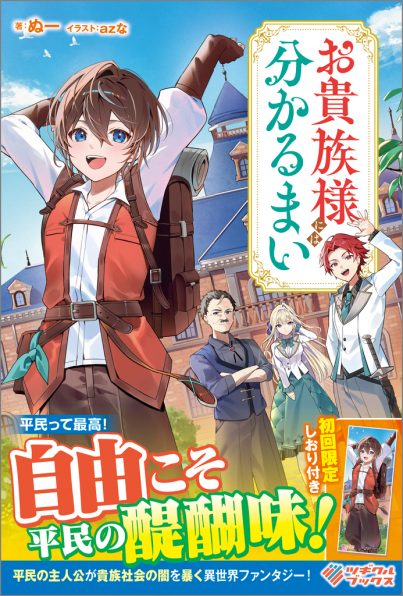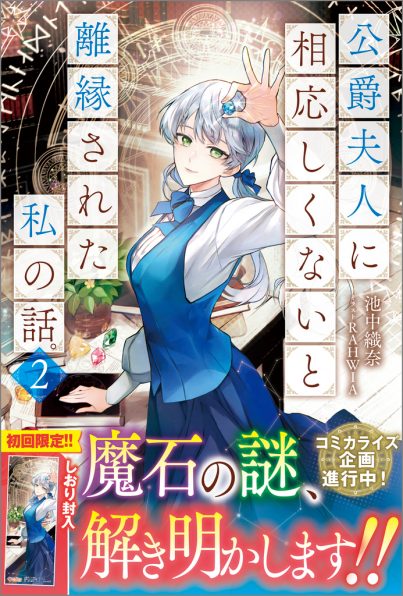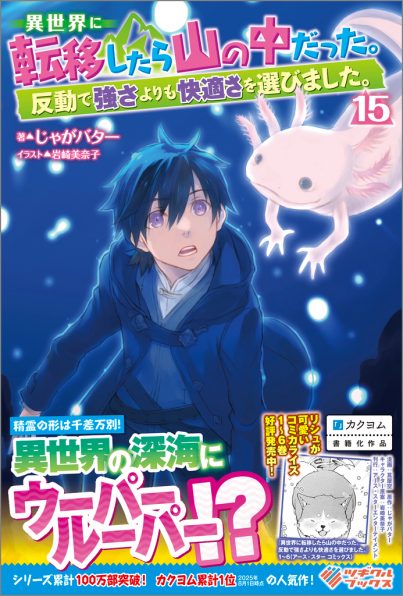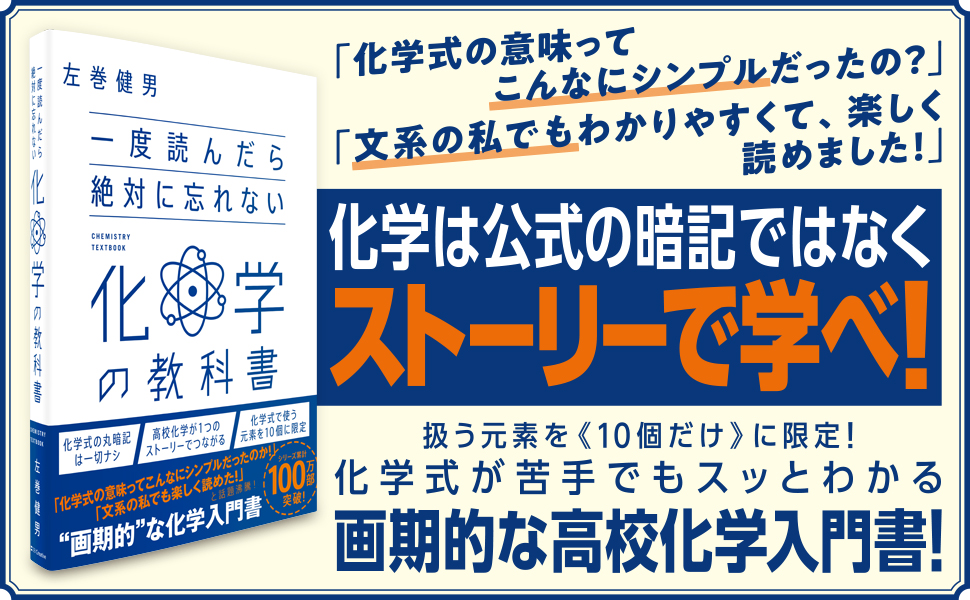
-

・そもそも“もの”ってなに?
・どんな物質も原子からできている
・原子は化学変化を繰り返しても不滅 -

・混合物を分離させると純物質が得られる
・元素名は「単体の場合」と「化合物の場合」がある
・固体・液体・気体では分子の「結びつき方」が変わる
・水は「固体⇔液体⇔気体」になるが物質自体は変わらない
・もとの物質から新たな物質に変化する「化学変化」
・「質量保存の法則」は物理変化でも化学変化でも成り立つ
・化学反応には「発熱反応」と「吸熱反応」がある
・まずはこれだけ! 元素記号と化学式
・「5H₂O」は「H₂Oが5個ある」ことを表す
・「炭素の燃焼」を「化学反応式」で表す …など -

・すべては火の利用から始まった
・古代ギリシアの原子論と四元素説
・2000年間栄えた錬金術が化学の礎に
・「空気に似た気体」の正体は「ガス」だった
・燃焼の正しい理論が確立し、「化学革命」が起こる
・二酸化炭素、窒素、酸素、水素が次々と発見される
・ラボアジェの化学革命に続いたドルトンの原子論
・元素が周期表にまとめられ、「物質界の地図」に -

・元素は「原子核の陽子の数」で区別する
・原子は、貴ガスの原子と同じ電子配置になりたがる
・陽イオンと陰イオンが「電気的に」つり合うイオン性物質
・非金属元素は「共有結合」で分子になる
・金属元素どうしが結びつく金属結合
・世の中の物質は大きく3つに分けられる
・身近だがとても例外的な性質がある水 -

・H:最も小さい原子・分子で地球上に水として存在
・C:生物の主要構成元素で有機化合物の世界をつくる
・N:空気の約78%を占める窒素ガス
・O:多くの元素と化合して酸化物をつくる酸素ガス
・Cl:人類初の毒ガス兵器(化学兵器)として使われた塩素ガス
・S:燃えると、有毒な亜硫酸ガス〔二酸化硫黄〕が発生
・Na:カッターナイフで簡単に切れるやわらかい金属
・Mg:まばゆい光で燃えて酸化マグネシウムになる金属
・Ca:骨、歯、殻などをつくる生体の主成分の1つ
・Al:アルミニウムは軽金属の代表的存在 -

・「重い・軽い」の1つの意味は「1体積あたりの質量」
・原子量は、水素原子1個の質量に原子質量単位uをつけて考える
・モルはミクロとマクロをつなぐ個数の単位
・質量パーセント濃度とppm、ppbという溶液の濃度の表し方
・質量パーセント濃度の他にモル濃度という溶液の濃度の表し方
・気体1molの体積は物質の種類にかかわりなく同じ
・ボイル・シャルルの法則から気体の分子運動と絶対温度がわかる!
・理想気体と実際の気体を区別して考える -

・高校化学の範囲ではほぼアレニウスの定義
・水中に水素イオンH+は存在しない
・温度が一定なら、水のイオン積は一定の値
・酸と塩基の中和では塩と水ができる
・酸と塩基が完全に中和するときに成り立つ関係式
・酸素なしで酸化還元を考える
・酸化数より、その反応が酸化還元かを判断できる
・電池はダニエル電池のしくみを理解する
・水の電気分解は水酸化ナトリウム水溶液を使う
・イオン化傾向が大きい金属は溶融塩電解で得る -

・有機物を無機物からつくることに成功
・なぜ、有機物を人工的につくることが難しかったのか?
・「電気陰性度」の値から見えてくる元素の性質
・結合の手4本で有機物の骨組みをつくる炭素原子
・エチレンは鎖状の不飽和炭化水素で最も簡単な構造の物質
・謎だったベンゼンの構造式を解明したケクレ
・官能基からどんな性質かがだいたいわかる
・メタノール、エタノールの性質を水と比べてみる
・酔いも二日酔いもエタノールのしわざ
・高分子化合物は、まずエチレンからポリエチレンの付加重合を理解