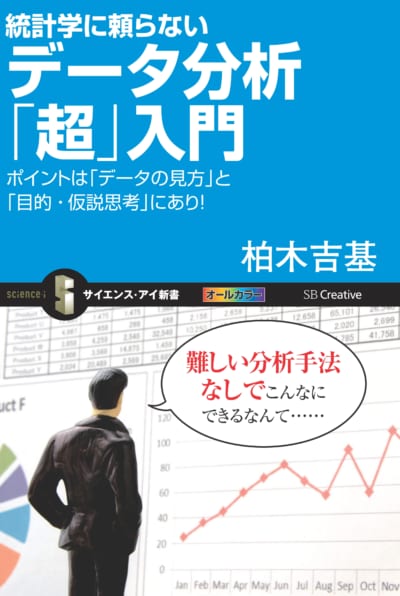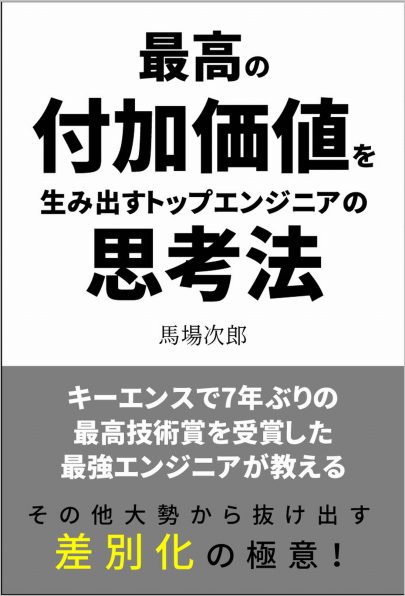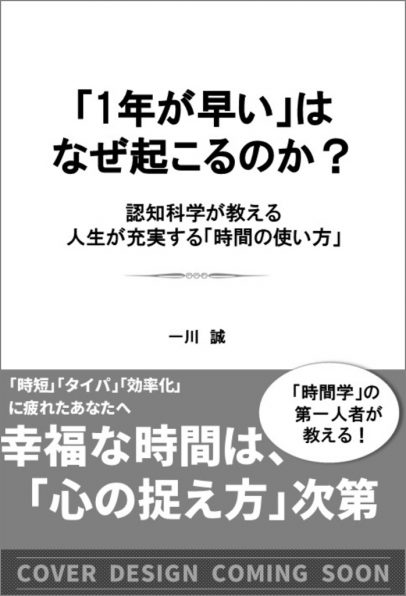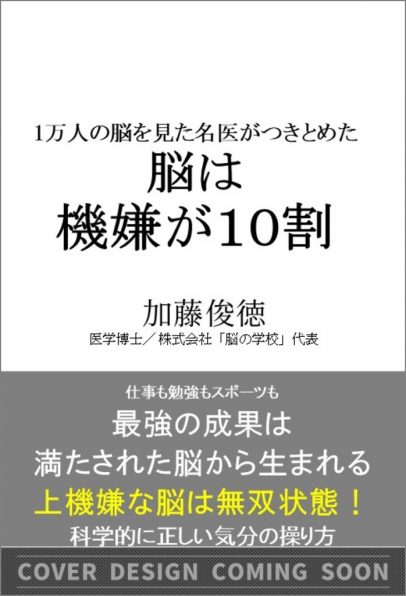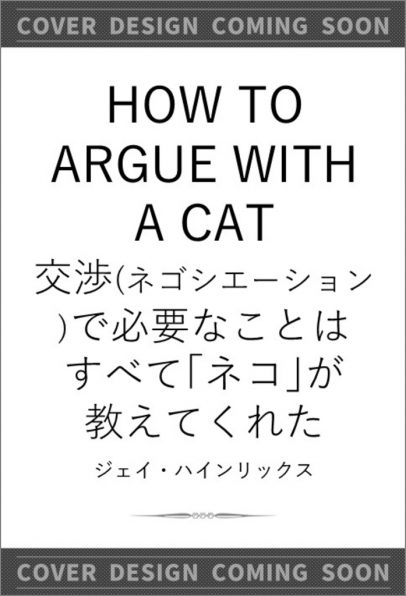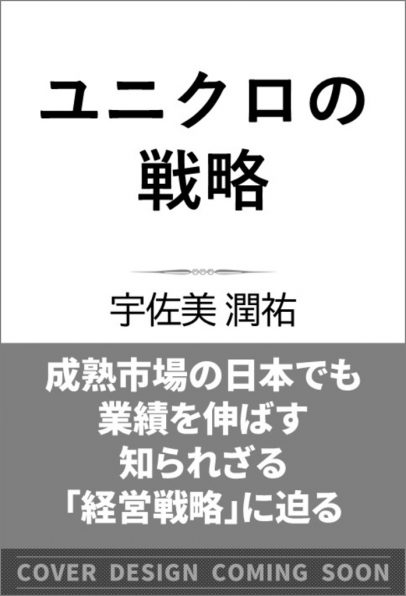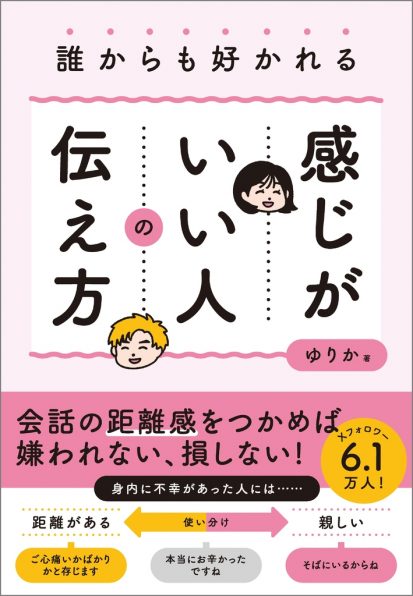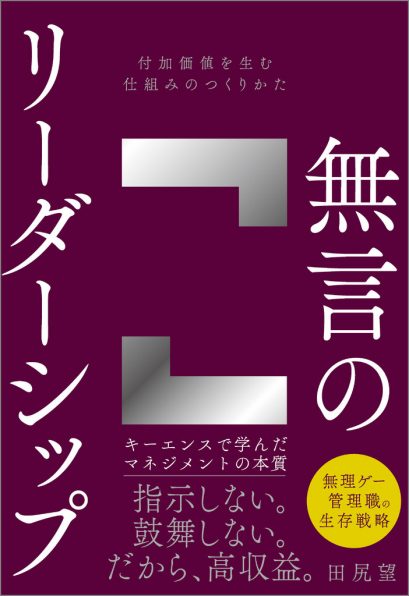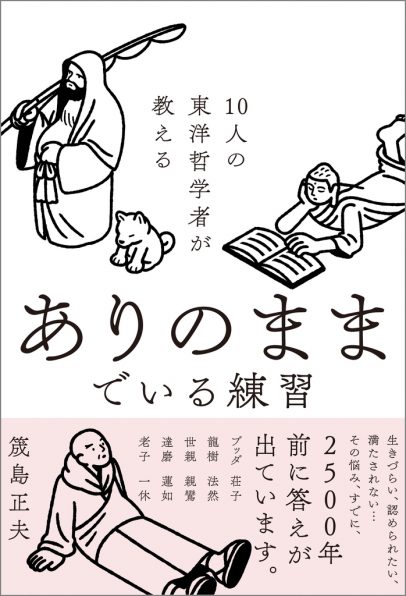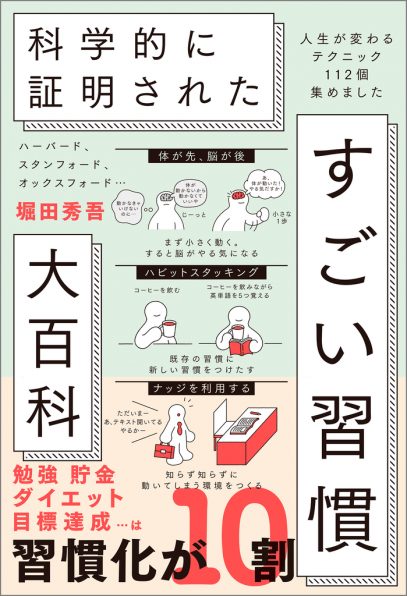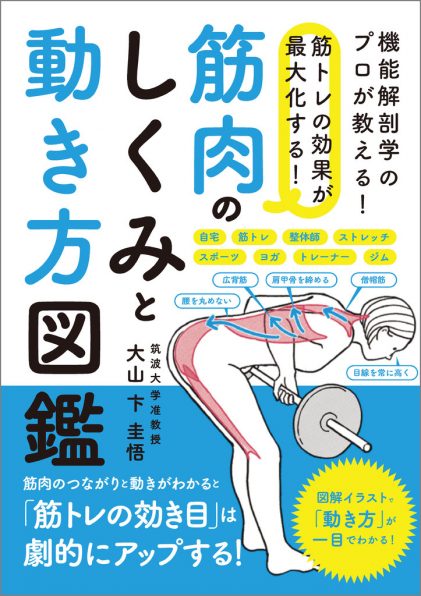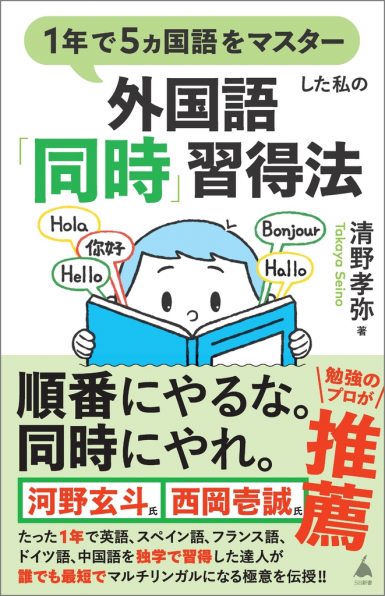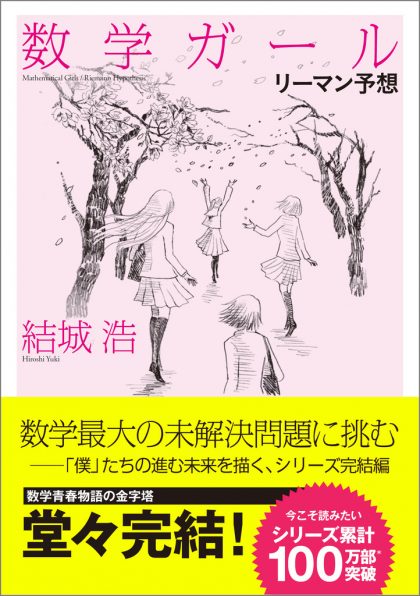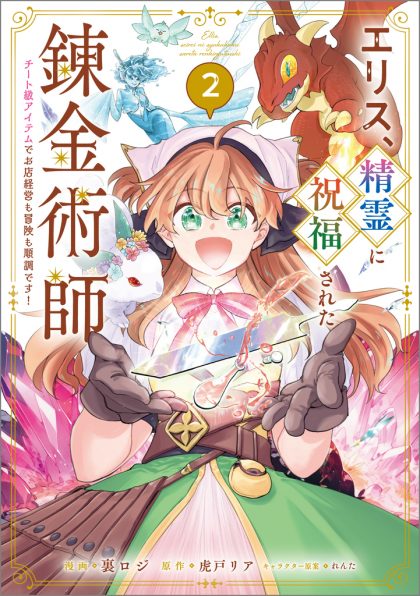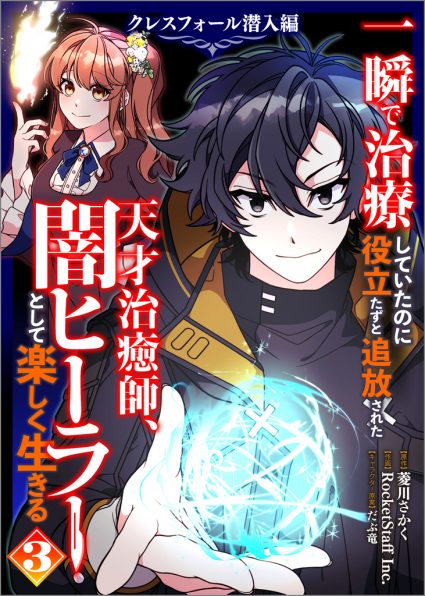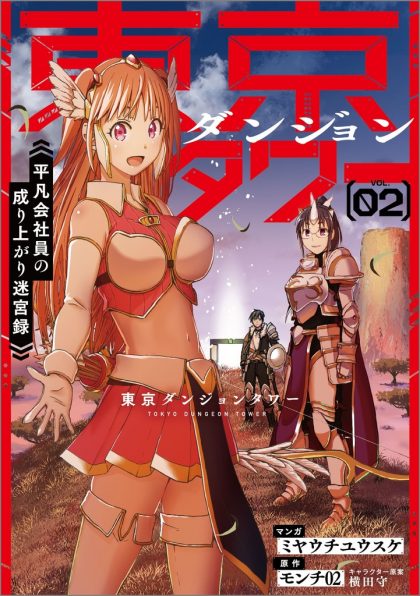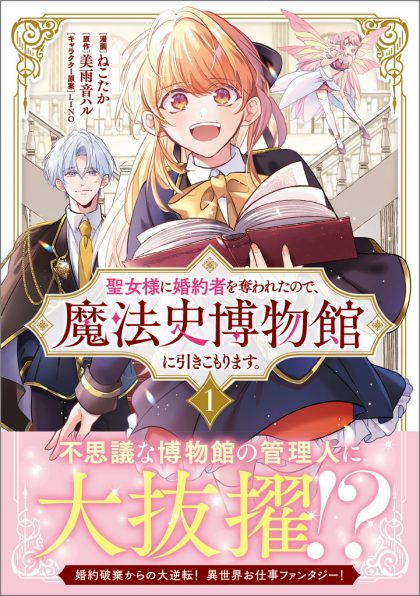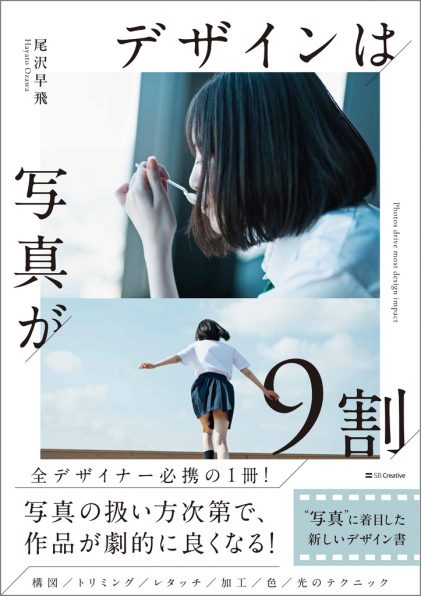それちょっと、数字で説明してくれる?と言われて困らない できる人のデータ・統計術
●グローバル企業で数々の提案を通した著者が、ビジネス最強の武器「数字×ロジカルシンキング」の使い方を紹介
「それ、数字で説明してくれる?」と言われて困った方、
経験で解決策を練ってきたもののうまくいかないことが多いと思っている方。
いつもグラフは作っているものの、その先に進みたいと思っている方。
分析手法は理解したけど、結局使えていないと悩んでいる方。
特に文系ビジネスパーソンのなかには、「数字」と言われるだけで、
何をどうしたらいいのかわからなくなる方も多いのではないでしょうか?
本書は、元日産で、外国人役員に数々の企画や提案を通した著者が、実務で数字を使いこなすためのロジカルシンキングや、 目の前の課題とデータとを結び付け、解決策にたどりつけるデータ分析の考え方、データを使った伝え方などを、紹介するものです。
●「数字×ロジカルシンキング」の両方があわさって、はじめて多角的な分析力が発揮される
たとえば、毎週の売上棒グラフを見て、「あの課は最下位だからなんとかしなければ」といったように、 単純な結論を出していませんか?
このような表面的な見方だけでは見落とす情報も多いのです。
ロジカルシンキングはできても数字が使えない、グラフ化などデータの整理はできてもロジカルな進め方や考え方ができないので、 適切な結論にたどり着かないという方は多いです。
本書では、初めて「数字」と「ロジカルシンキング」を組合わせ、データ分析をする前に絶対必要となる考えの組み立て方を中心に紹介する本です。
課題定義から解決策まで、主人公の洋平と一緒に、一連の流れを追いながら、
ゆっくり解説していきますので、分析手法だけにとどまらない「考え方」を知ることができます。
■目次:
序章 それ、ちょっと数字で説明してくれる?ってどういうこと?
第1章 数字やデータで考えるための「ロジカルシンキング」
Story 「本当の課題」をデータで再度考えよう?
第2章 現状を知り、「課題」(What)を特定する
Story 「なんでA商品が問題って言えるの?」「そ、それは~」
第3章 データで「なぜ問題が起こっているのか」(Why)を確認する
Story「商品寿命が終わったって本当?」
第4章 結果を伝える
Story 今までの話を整理する