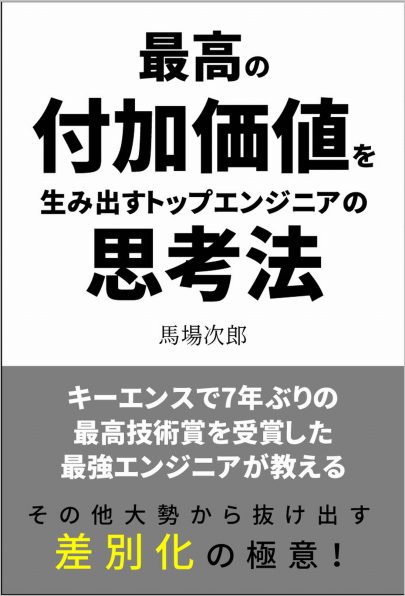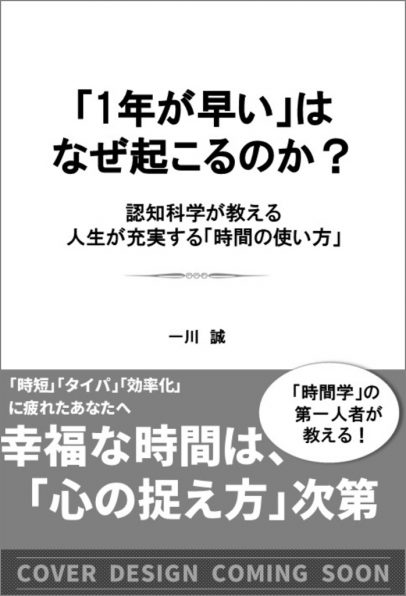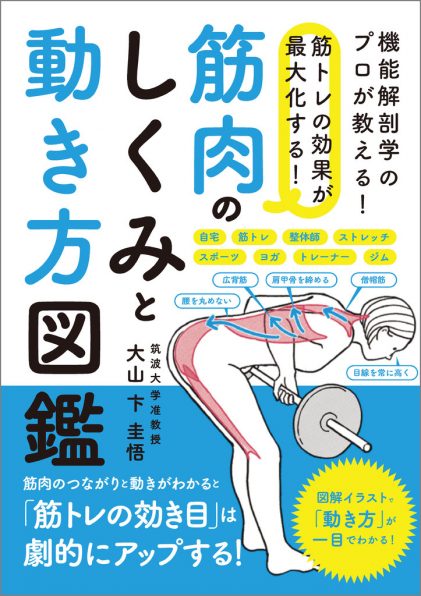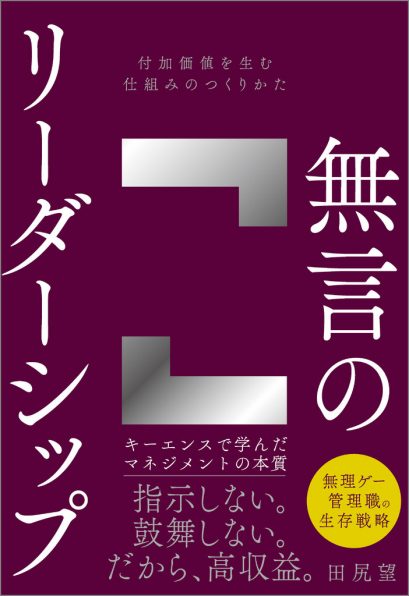ディズニー サービスの神様が教えてくれたこと
リピート率9割以上を誇り、日本でいちばん顧客満足度が高いと言われるディズニーランド。
その秘密は、実は「サービスの神様」が握っていた。本書はキャストとゲストの交流を描いた4つの感動物語からディズニーの奇跡のおもてなし、その極意を紹介する。
【目次】
第1話 オレンジ色のラブレター
第2話 迷子の良心
第3話 色あせたチケット
第4話 希望のかけ橋
■著者:鎌田 洋(かまた ひろし)
1950年、宮城県生まれ。商社、ハウスメーカー勤務を経て、1982年、(株)オリエンタルランド入社。東京ディズニーランドオープンに伴い、初代ナイトカストーディアル(夜間の清掃部門)・トレーナー兼エリアスーパーバイザーとして、ナイトカストーディアル・キャストを育成する。
その間、ウォルト・ディズニーがこよなく信頼を寄せていた、アメリカのディズニーランドの初代カストーディアル・マネージャー、チャック・ボヤージン氏から2年間にわたり直接指導を受ける。その後、デイカストーディアルとしてディズニーのクオリティ・サービスを実践した後、 1990年、ディズニー・ユニバーシティ(教育部門)にて、教育部長代理としてオリエンタルランド全スタッフを指導、育成する。1997年、(株)フランクリン・コヴィー・ジャパン代表取締役副社長を経て、1999年、(株)ヴィジョナリー・ジャパンを設立、代表取締役に就任。著書に『ディズニーそうじの神様が教えてくれたこと』(ソフトバンククリエイティブ)、『ディズニーの絆力』(アスコム)がある。