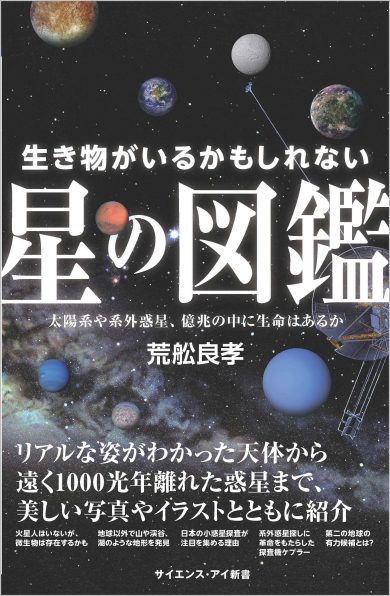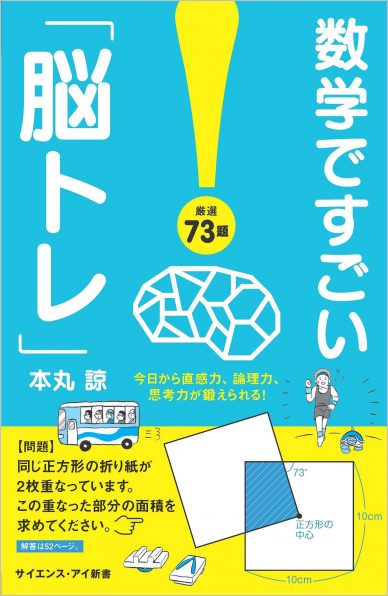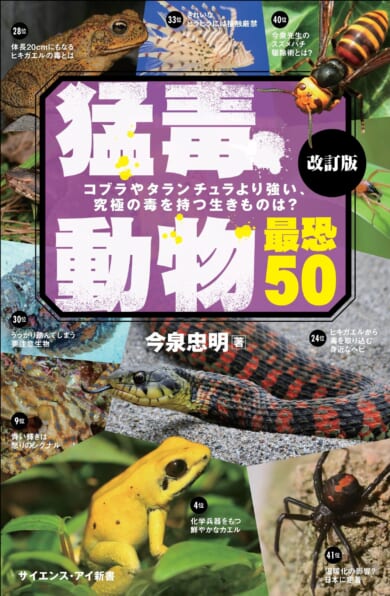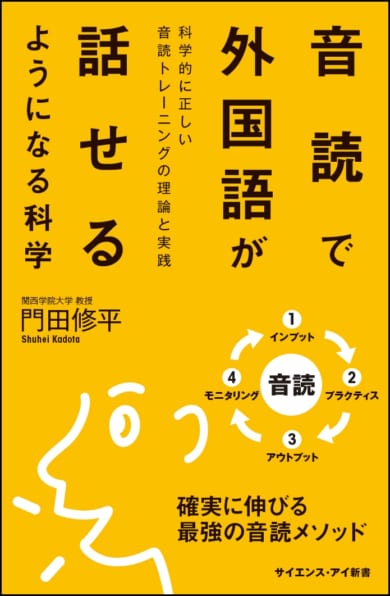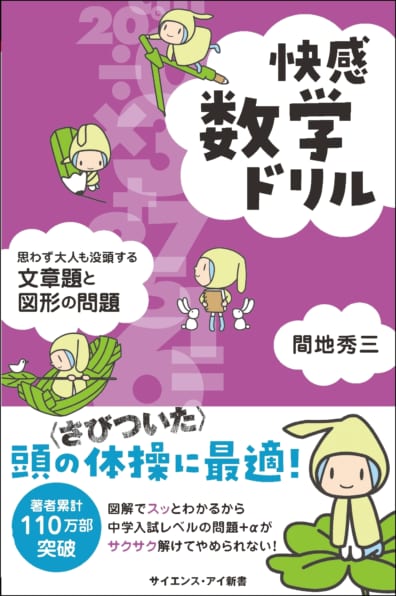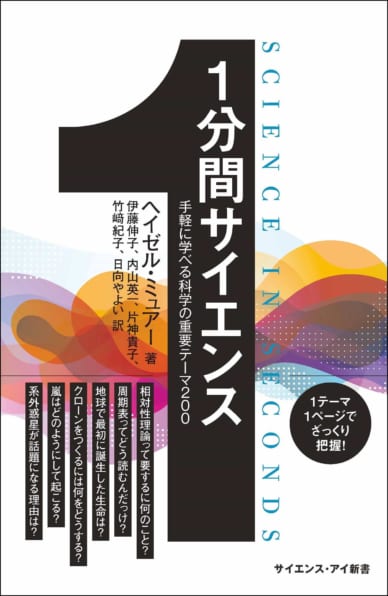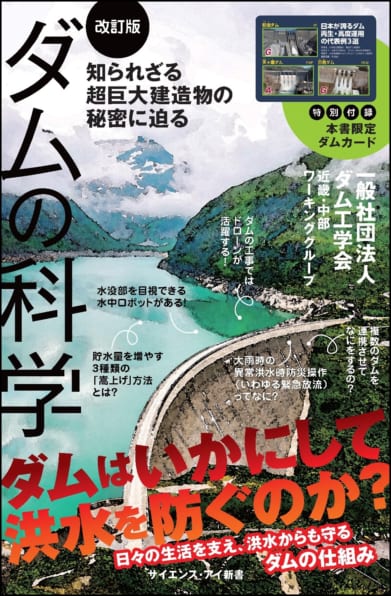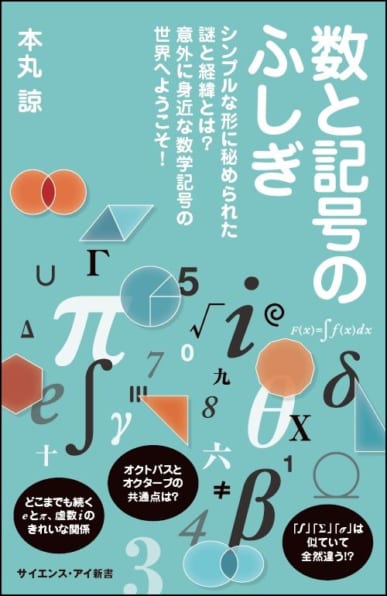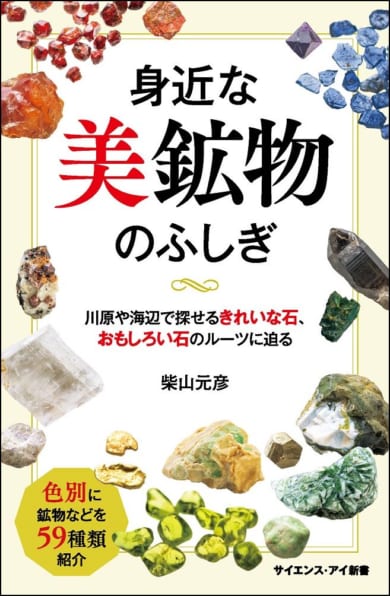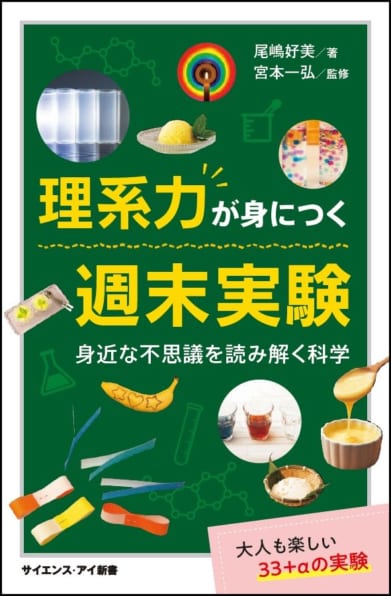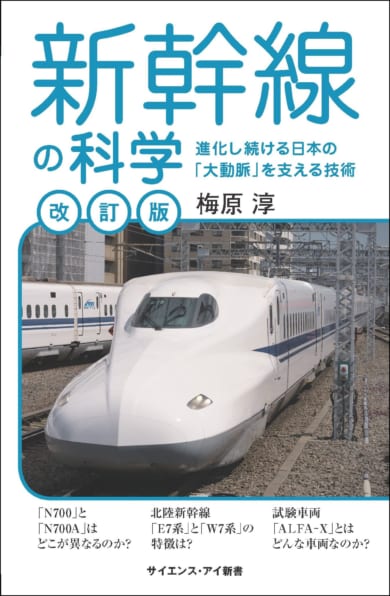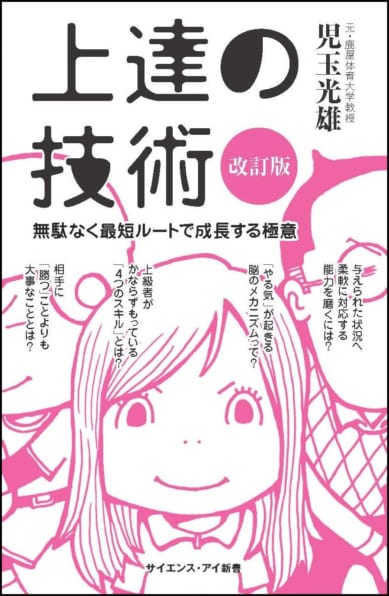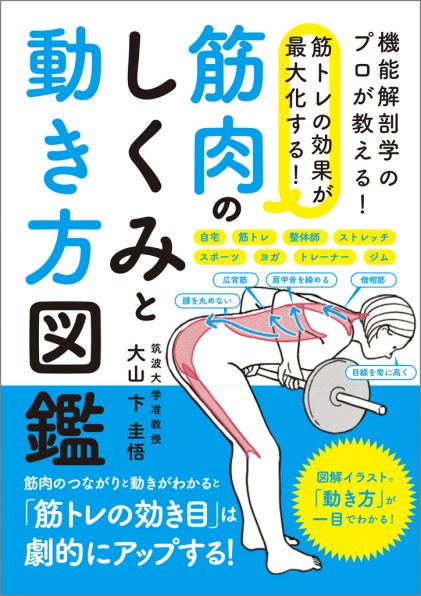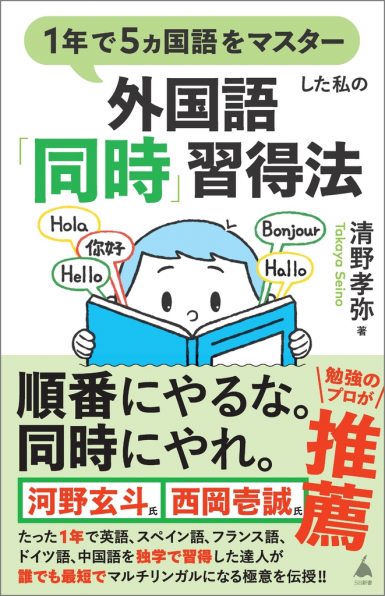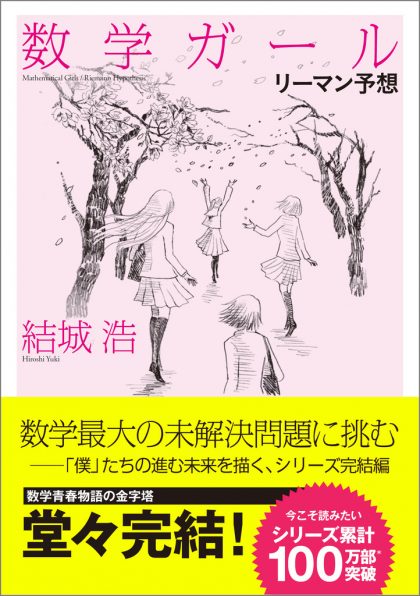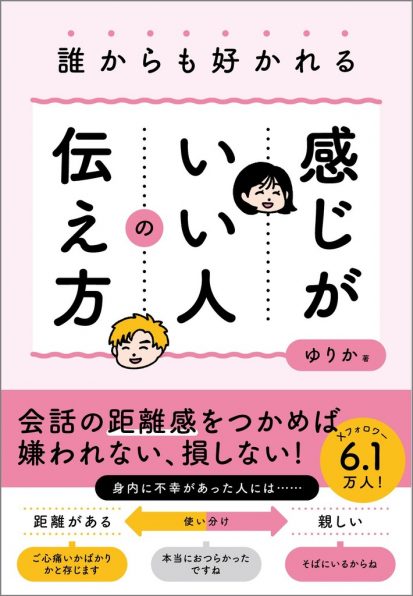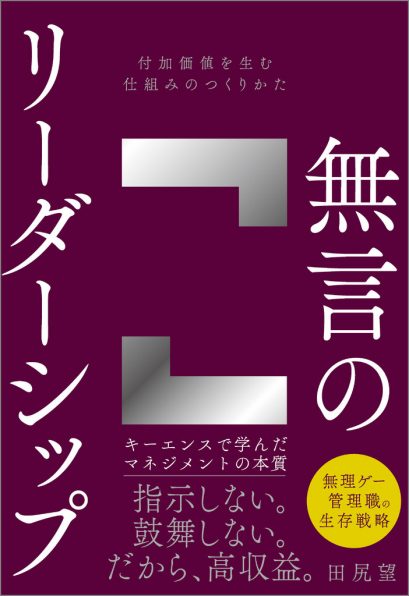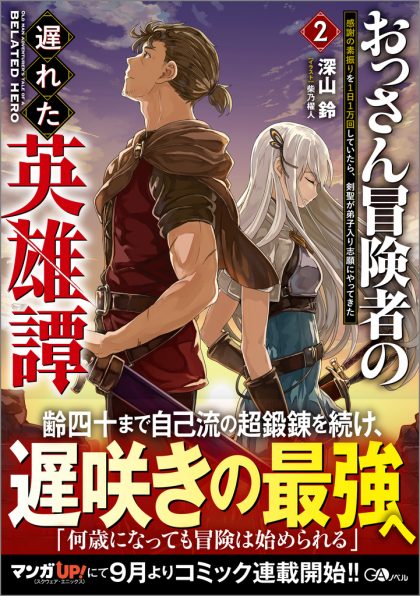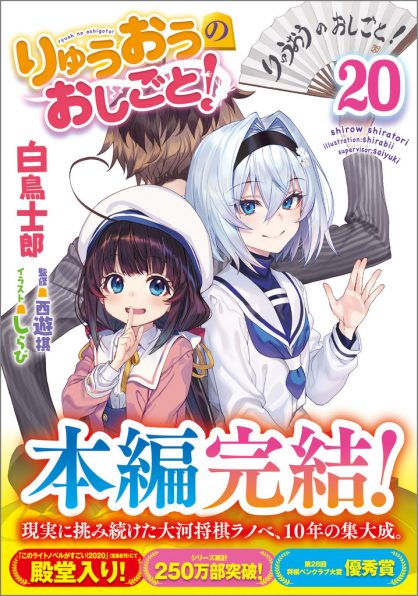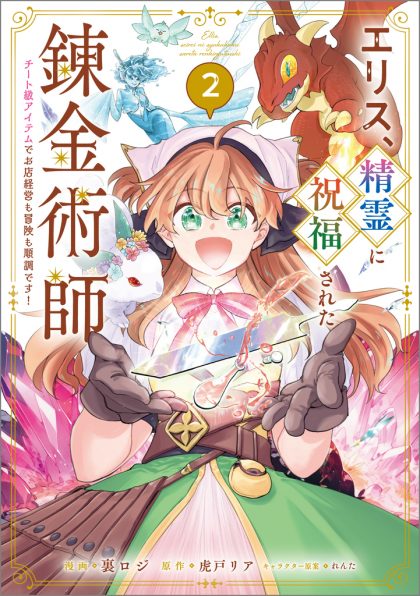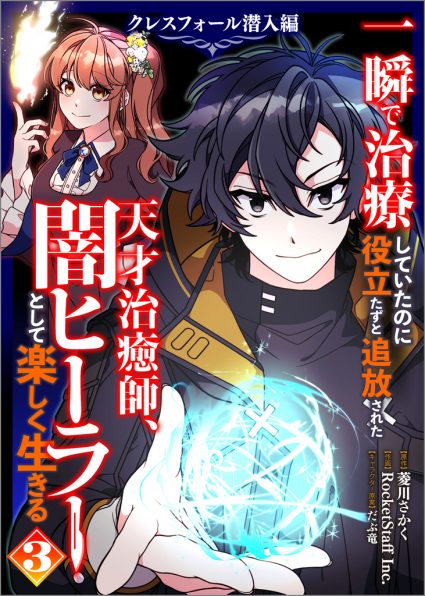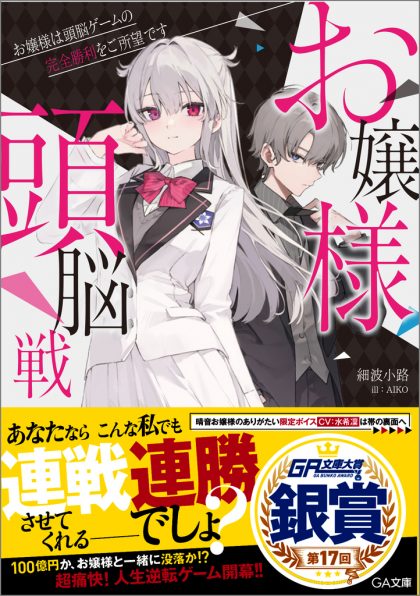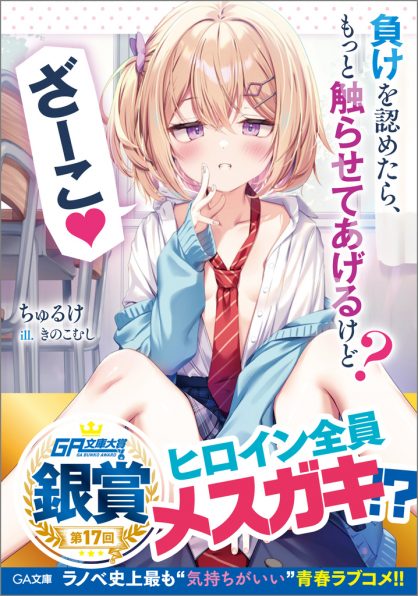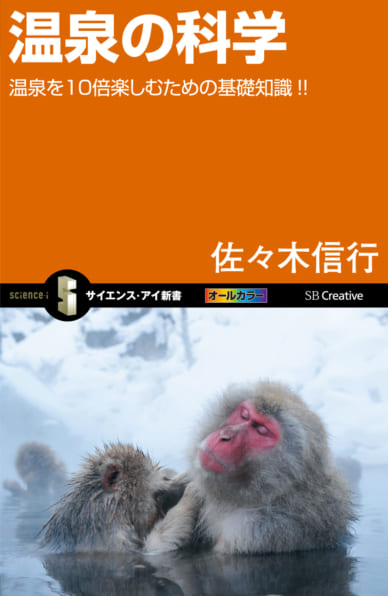
[Si新書]温泉の科学
温泉を10倍楽しむための基礎知識!!
人は古代から心と身体を癒すのに、温泉を積極的に活用してきました。ただ、温泉にも天然と人工があり、また泉質によって効能が変わります。そこで本書では、温泉とはなにかという基礎知識から、入浴法、飲泉やタラソテラピーといった活用法までを解説します。
■目次:
第1章 温泉とは
第2章 温泉の性質と分類
第3章 温泉の分布と熱
第4章 温泉の効能と利用法
第5章 温泉の起源と変化
第6章 温泉に関する法律と温泉環境
第7章 温泉の管理と衛生
第8章 温泉の歴史と文化
第9章 温泉の名物
第10章 現代の温泉の課題