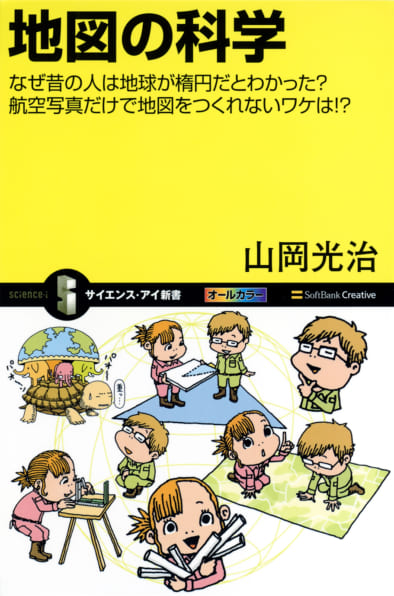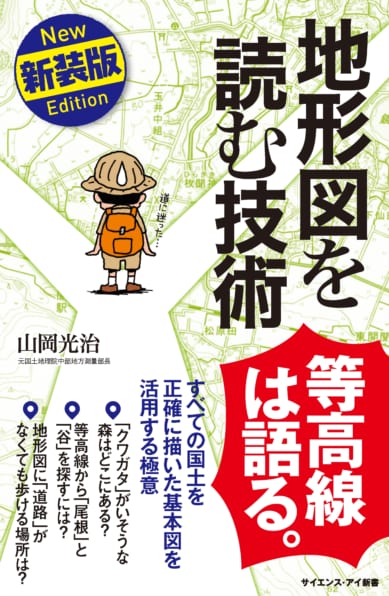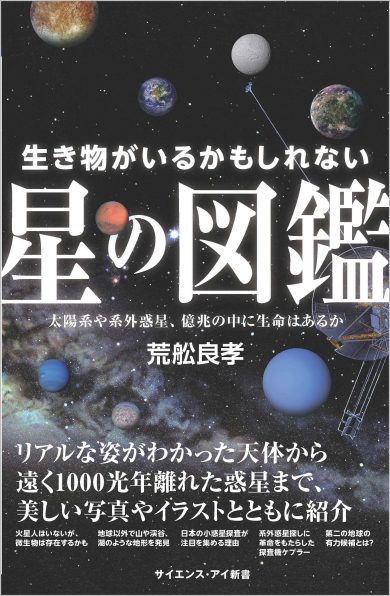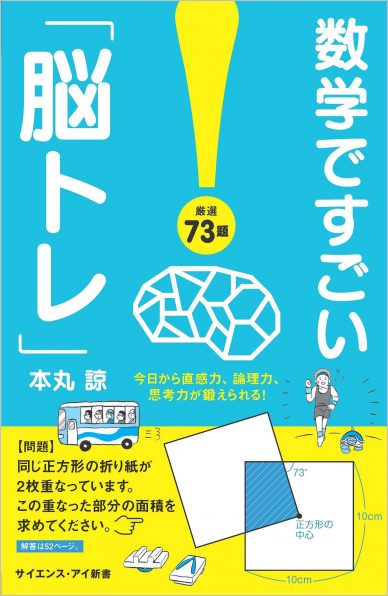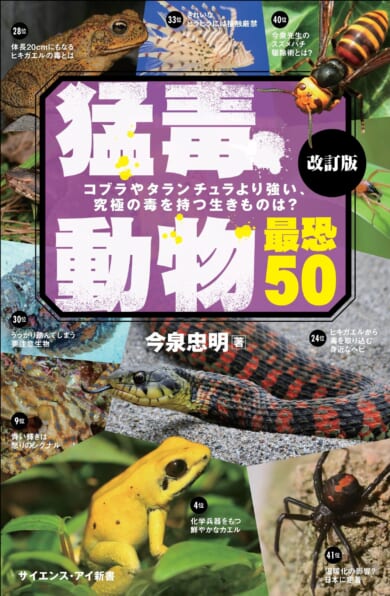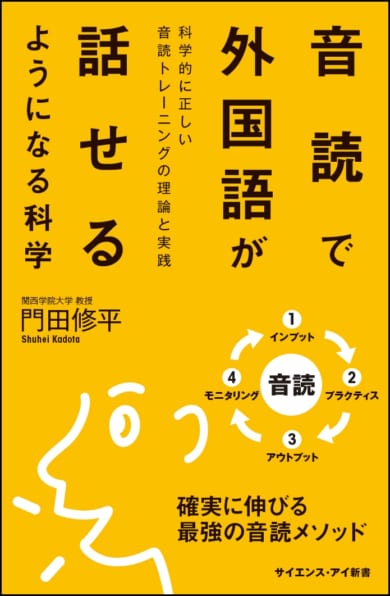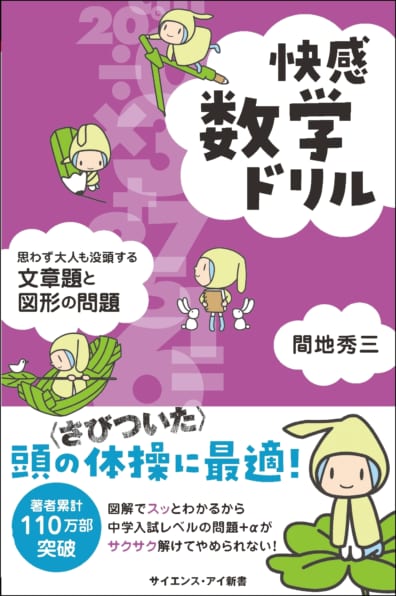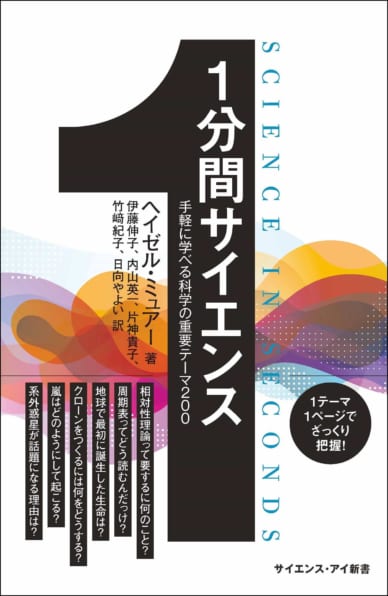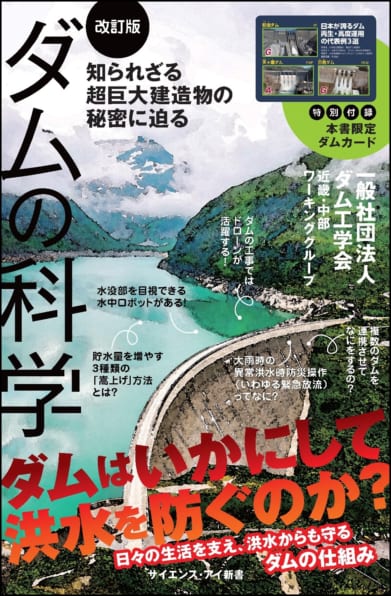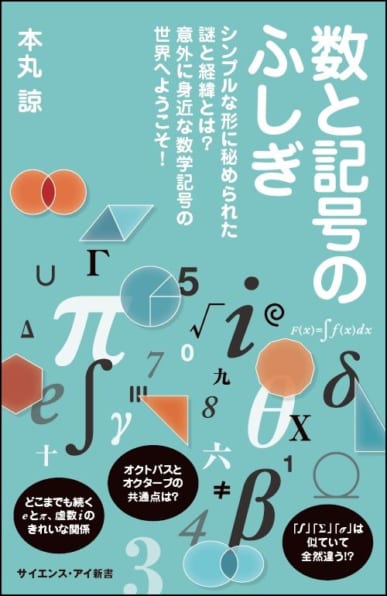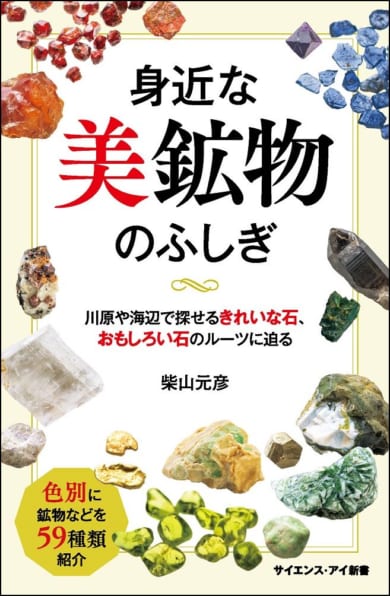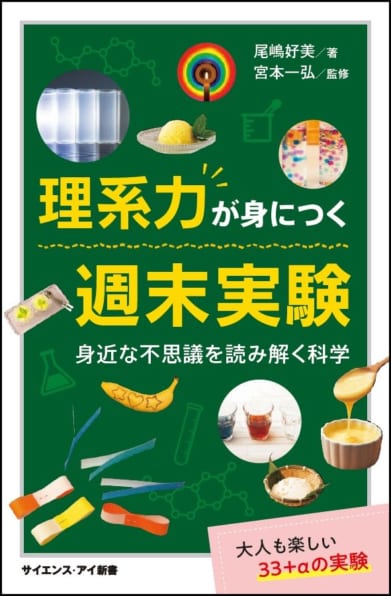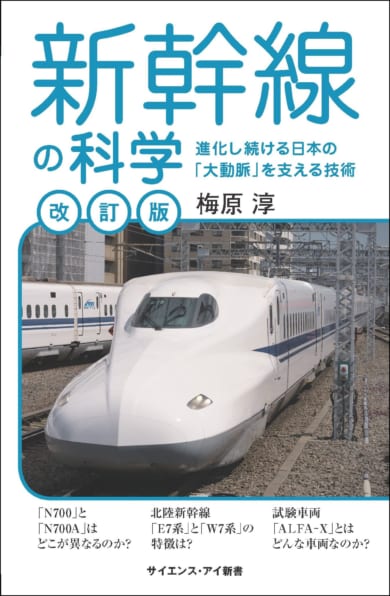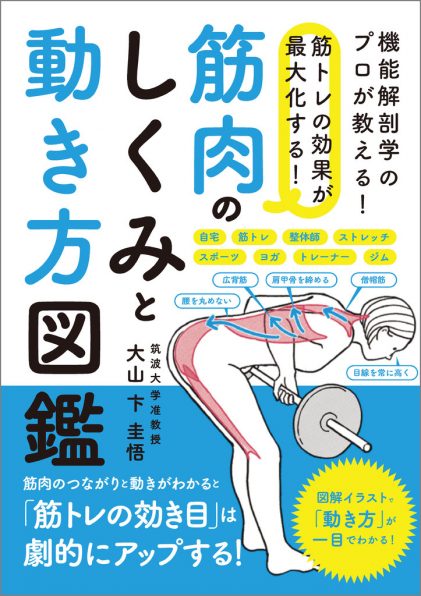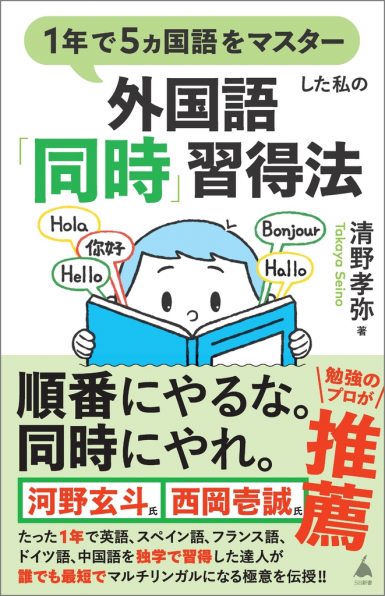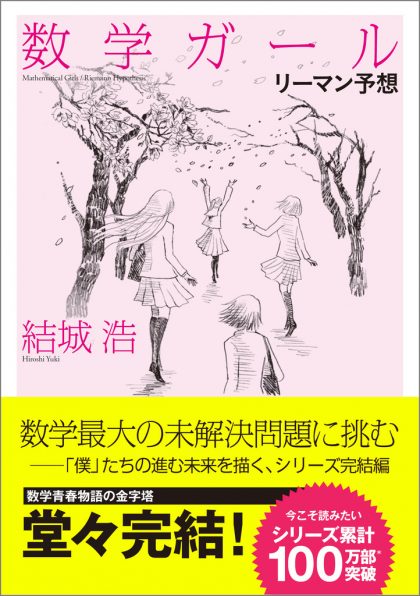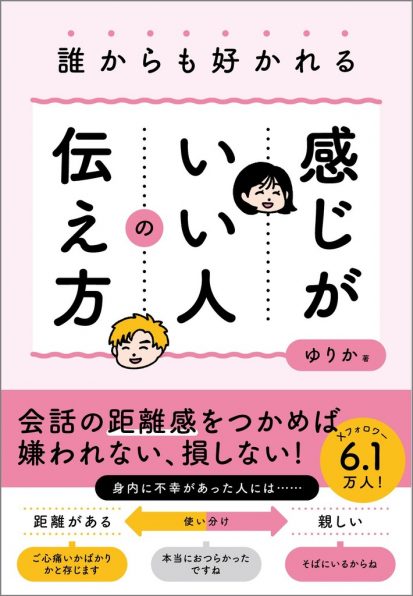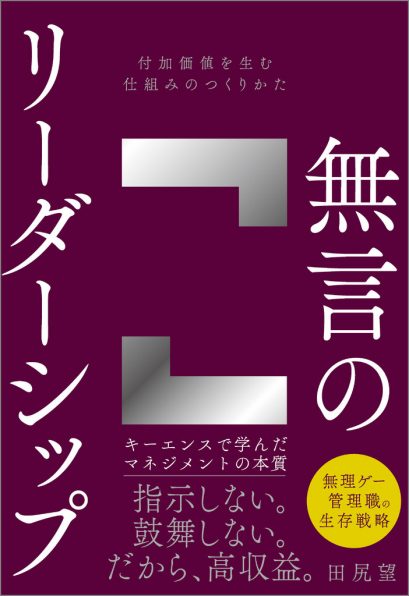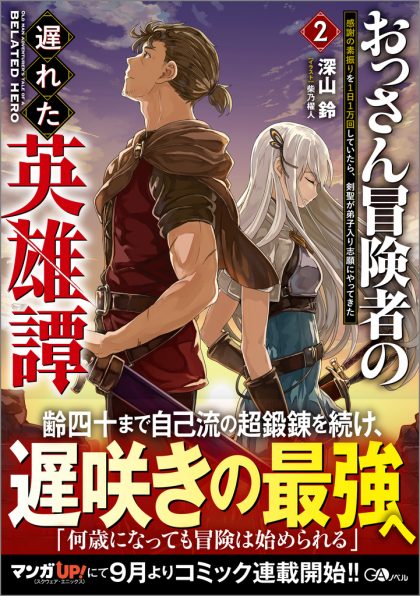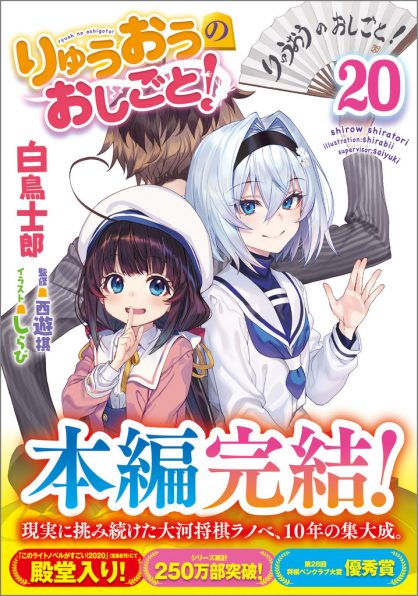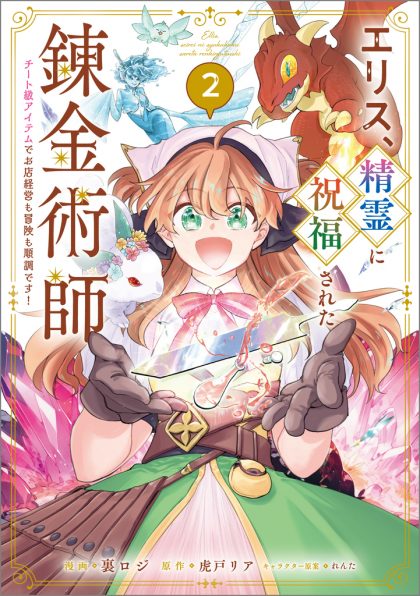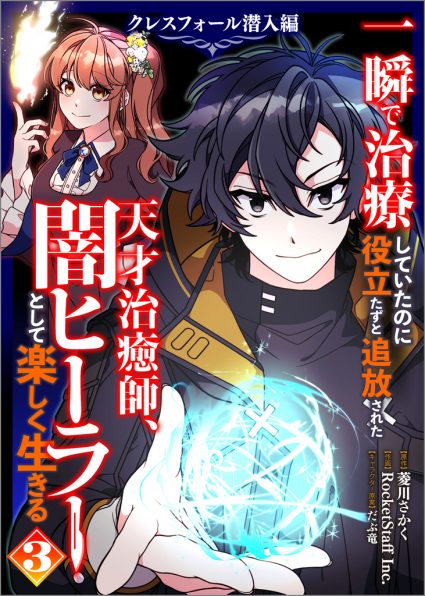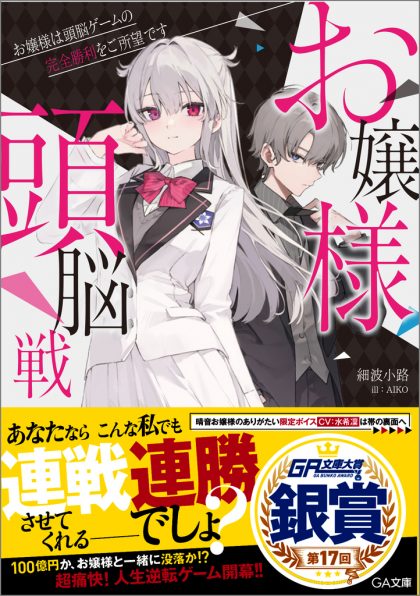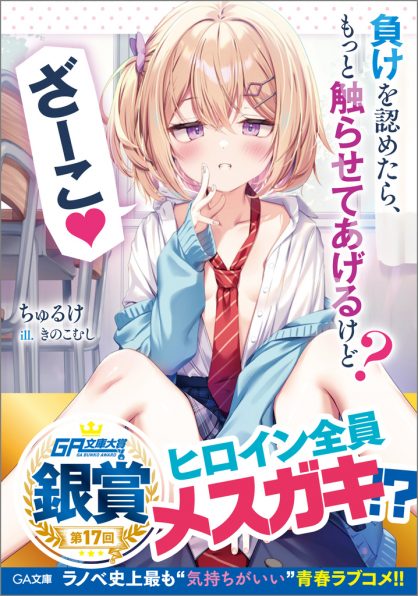[Si新書]地図の科学
なぜ昔の人は地球が楕円だとわかった?航空写真だけで地図をつくれないワケは!?
「地図」を見たことがない人はおそらくいないでしょう。でも、地図をつくるときに数学や物理が欠かせないことをご存じでしょうか? 本書では地図のキホンから、さまざまな地図の解説、地図の読み方、地図をつくるための技術まで解説していきます。
■第1章 人はなぜ地図をつくる?
1.1 地図とはどのようなものか?
1.2 人はなぜ地図をつくる?
1.3 最古の世界図はどこにある?
1.4 地球は円盤状か? 球体状か?
1.5 やっぱり地球は球体だ!
■第2章 人は、なぜ道に迷うのか?
2.1 「頭脳の地図」と「はじめてのお使い」
2.2 人は、地図があっても道に迷う?
2.3 人は、なぜ地図を必要とするか?
2.4 正しい地図の歩き方 1
1)どのような地図があるのか
2)地図の外側も読む
Column ** 鳥瞰図と蛙瞰図 **
3)近代地図作りのこれまで
Column ** 伊能忠敬の測量法or測量機器 **
■第3章 地図から現在を読み、過去を読む
3.1 なぜ「地図を読む」というのだろうか?
3.2 地図からなにを、どう読むのか
3.3 地図からなにが読めないか、ウソはないのか
3.4 平面の地図から立体を読む
1)平面のなかに立体を読む
2)等高線から立体を読む
3.5 等高線が読めるとなにがわかるか
■第4章 地図は、どうやってつくられているか?
4.1 地球の大きさと形を知る
1)地球の大きさを知る
・緯度を知る
・経度を知る
2)地球の形を知る
3)星を眺めて、経緯度原点をつくる
4)海を眺めて、水準原点をつくる
5)角を測って日本中に三角点の網をつくる
・三角測量から、三辺測量へ
・横から縦へ、GPS測量
6)高さを測って日本中に水準点の網をつくる
7)海の向こうへどうつなげたか?
4.2 地図作成の実態
1)地球(球体)から地図(平面)へ
・おもな投影法
2)平面の地図に、ひずみはないのか?
・投影法と特徴、そして使い方
3)平板測量と、写真測量による、これまでの地図つくり
・空中写真撮影
・図化と編集
4)現在とこれからの地図作り
5)どこまでも続く地図の更新
・地図はどう使われているか?
6)実際に地図を作成してみよう
■著者:山岡光治
1945年、横須賀市生まれ。1963年、国土地理院に技官として入所。札幌、つくば、富山、名古屋などの勤務を経て、2001年、同院退職。同年、地図会社のゼンリンに勤務。2005年、地図測量を楽しくやさしく紹介するための「オフィス地図豆」を開業。日本各地の地図愛好家、天文史研究家と交流。執筆や講演会、市民講座などでの地図作成実演などを通じて、地図測量への理解を深める活動をしている。『地図に訊け!』(ちくま新書)、『地図を楽しもう』(岩波ジュニア新書)などを執筆。2009年10月には「タモリ倶楽部」にも出演。