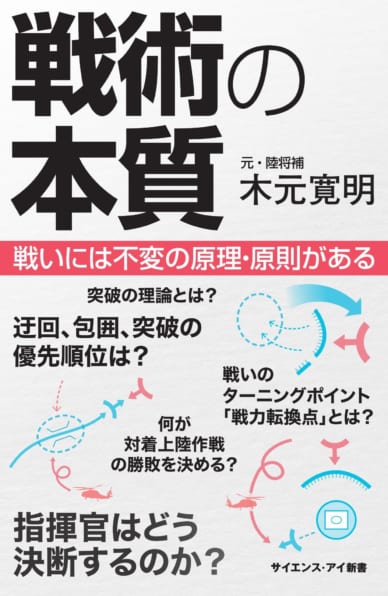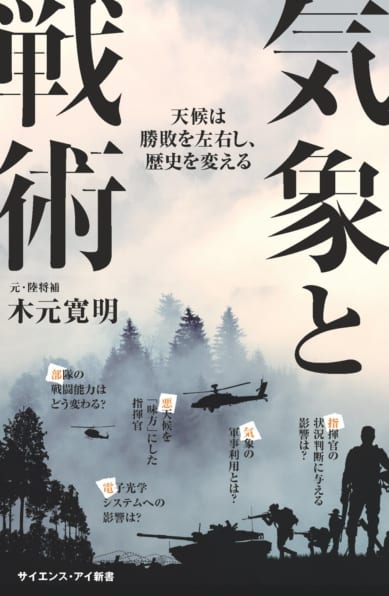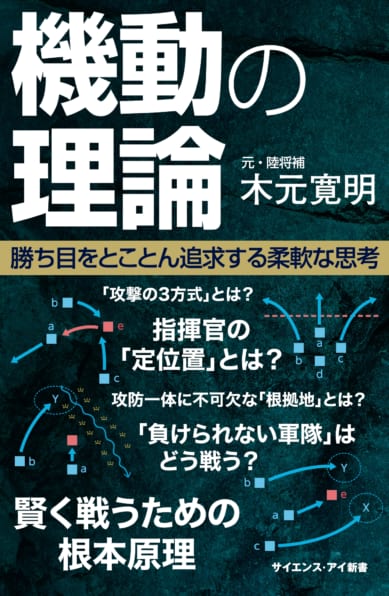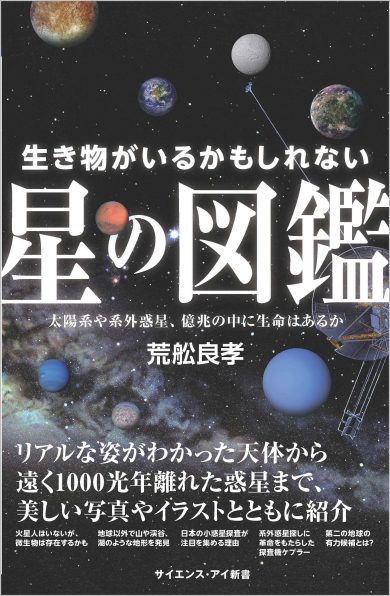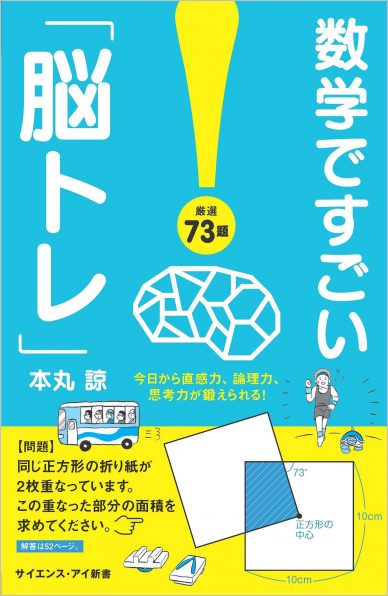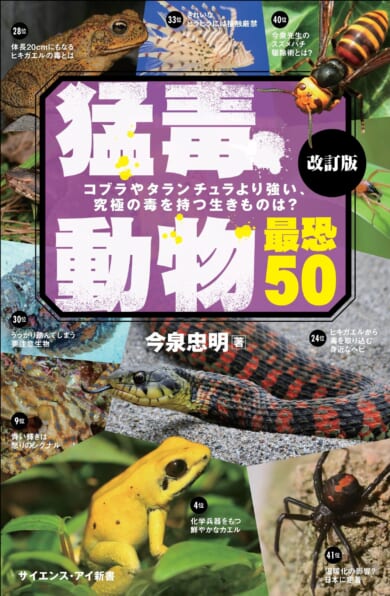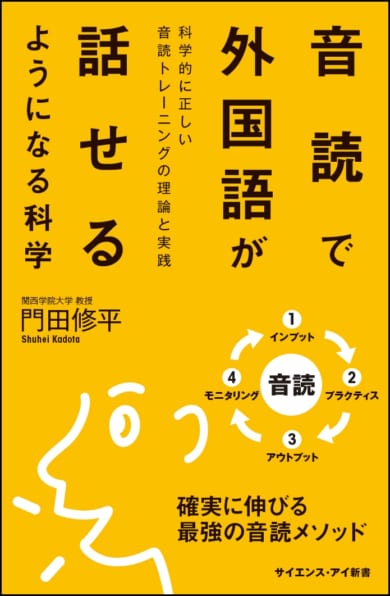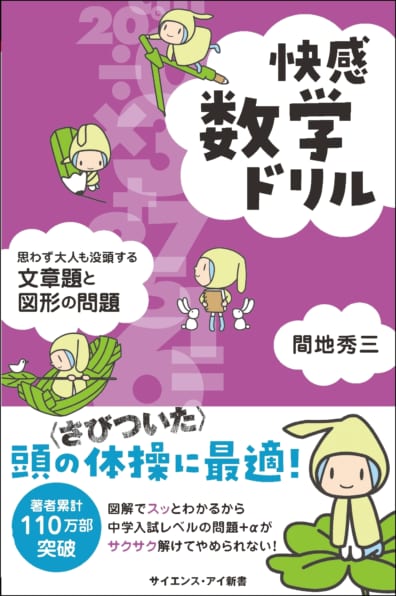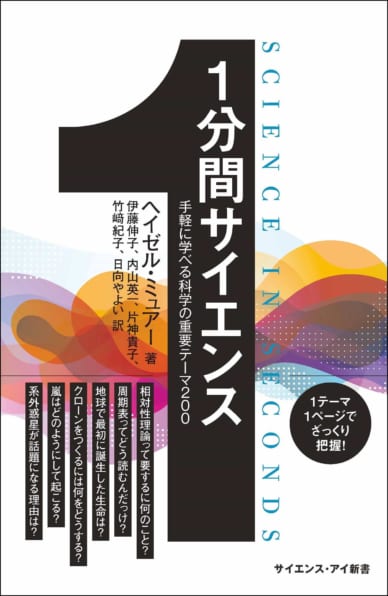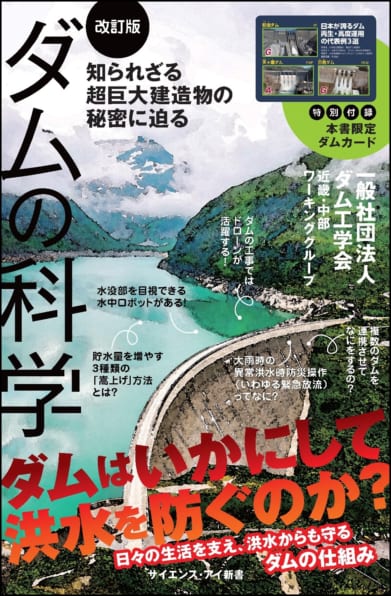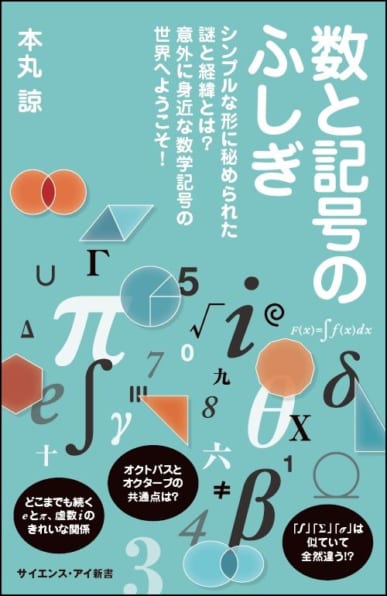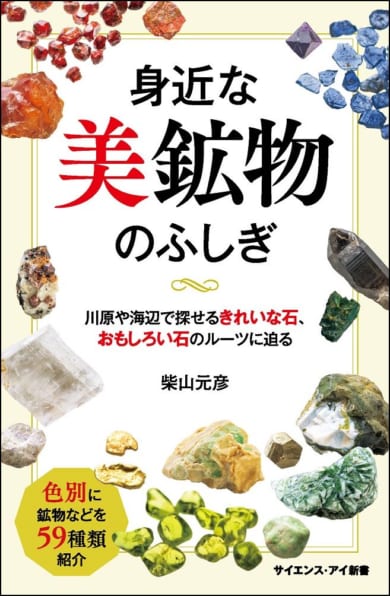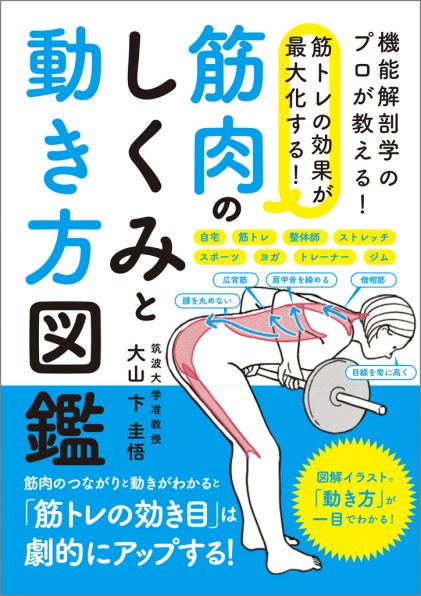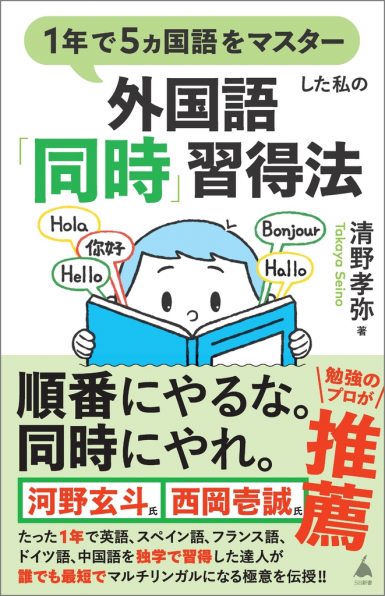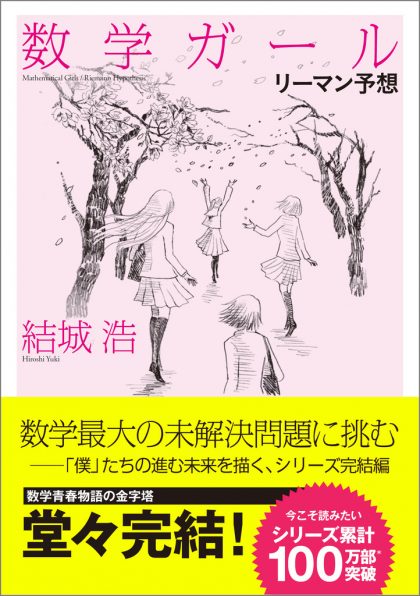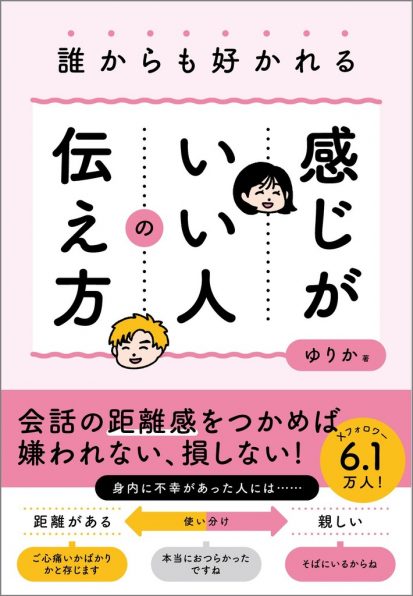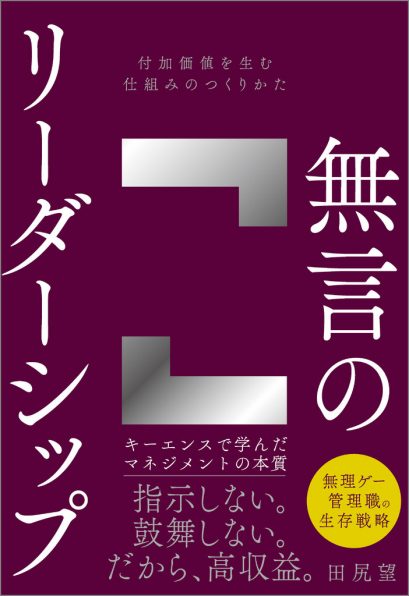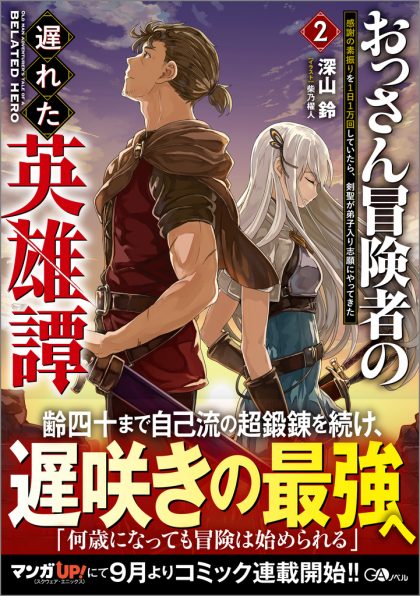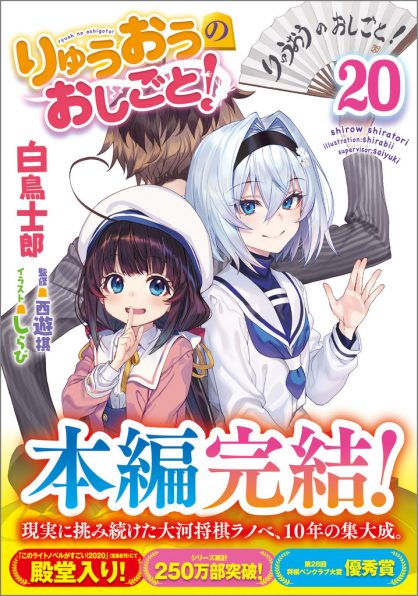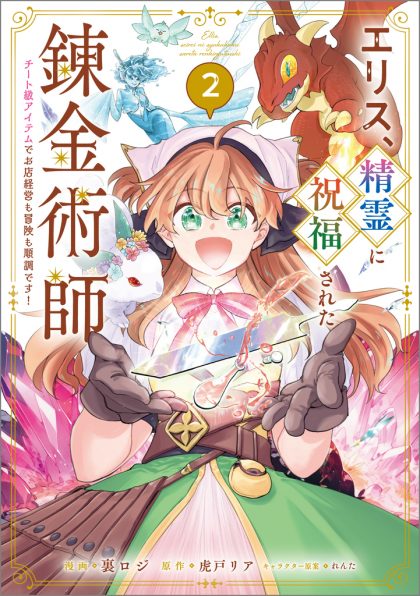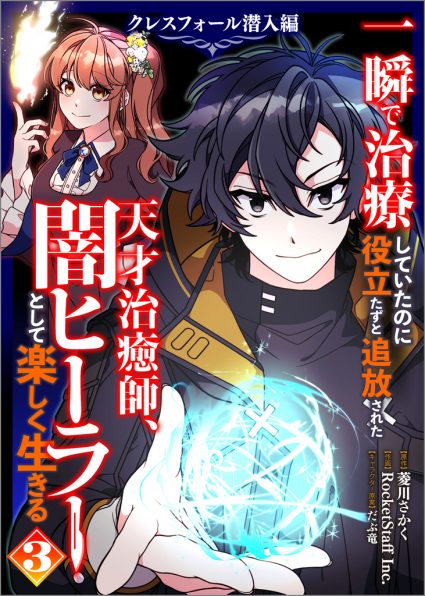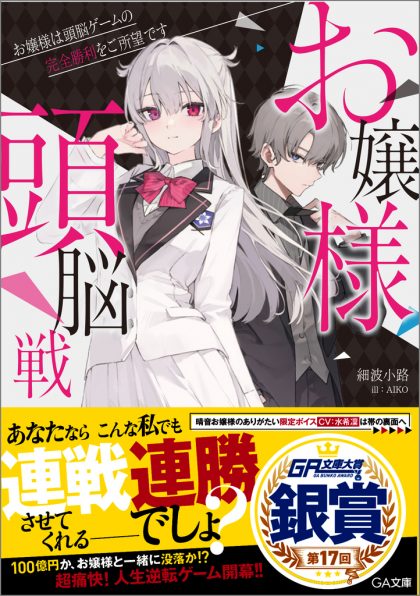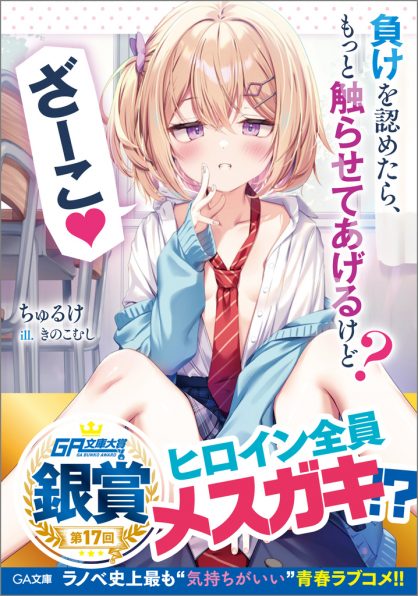[Si新書]戦術の本質
戦いには不変の原理・原則がある
北海道の機甲科部隊・第71戦車連隊の連隊長をつとめた戦車戦闘のプロフェッショナル・木元寛明氏(元・陸将補)が、「戦術の本質」を1冊にまとめました! 】
リアリズムが支配する現代の戦場で、指揮官はどのように作戦を立案し、どうやって部隊を指揮・運用し、敵を撃破し、勝利を収めるのでしょうか? 勝利の「原理・原則」や「方程式」はあるのでしょうか? 本書では、陸上自衛隊で陸将補を務めた著者が、戦術を体系的に解説し、その本質に迫ります。また、兵法書として名高い『孫子』は、多くのビジネスマンに愛読されています。戦術を知ることは、ビジネスの世界での勝利にもつながることでしょう。
■目次:
第1章 戦いには不変の原則がある
第2章 戦いの基盤
第3章 戦いのサイエンス
第4章 戦いのアート~指揮官の決断
第5章 アートとサイエンスの叙事詩~戦史の華