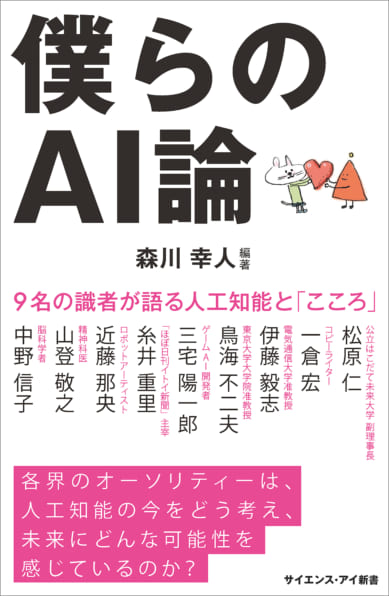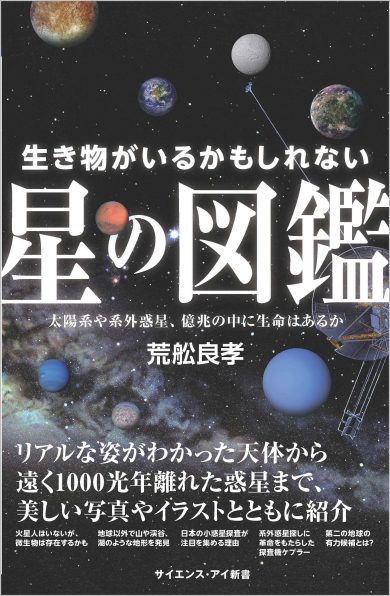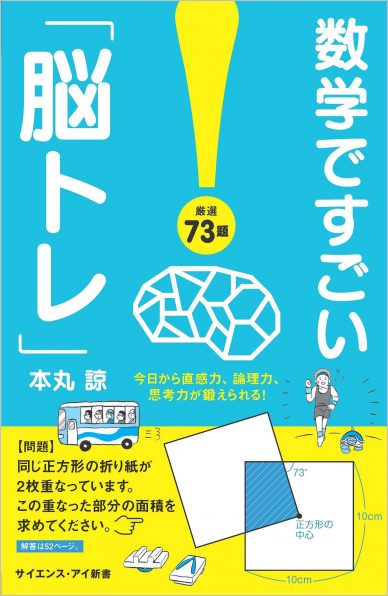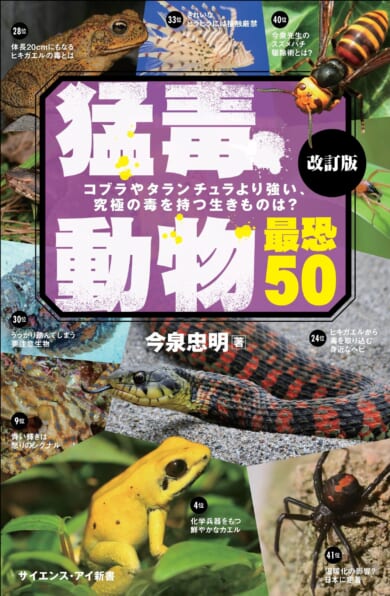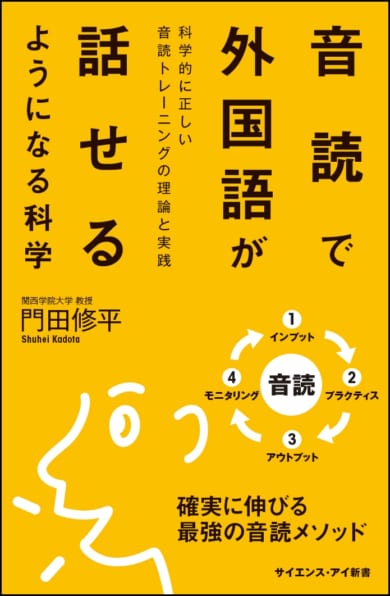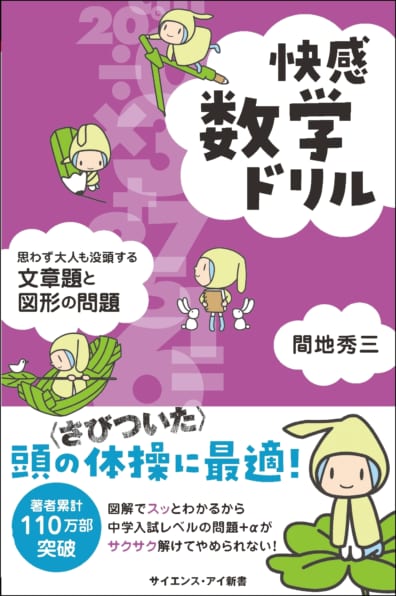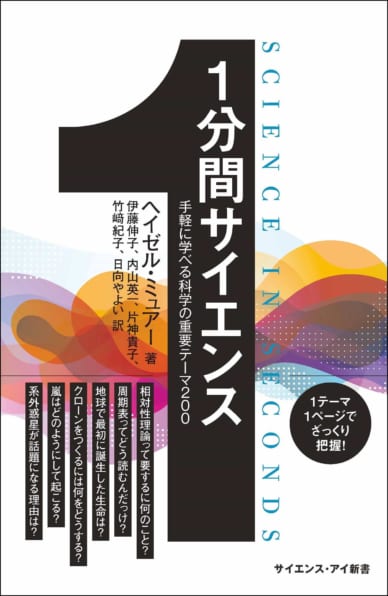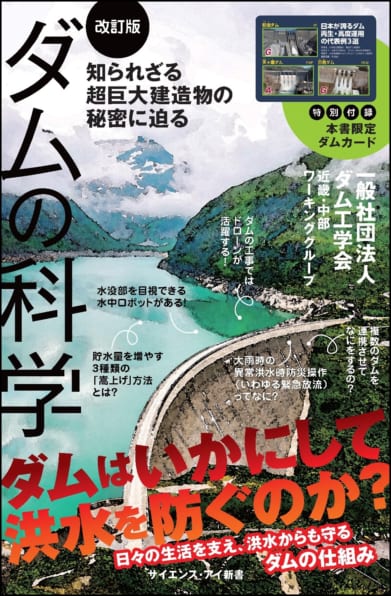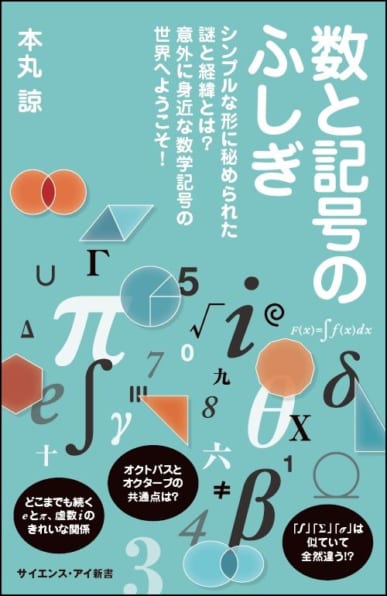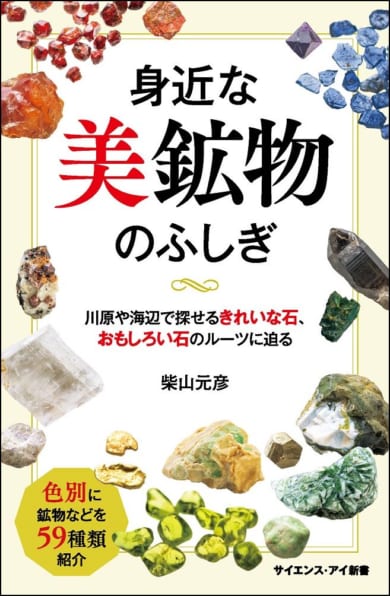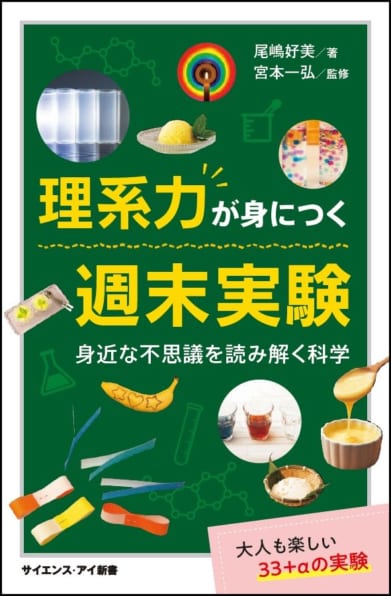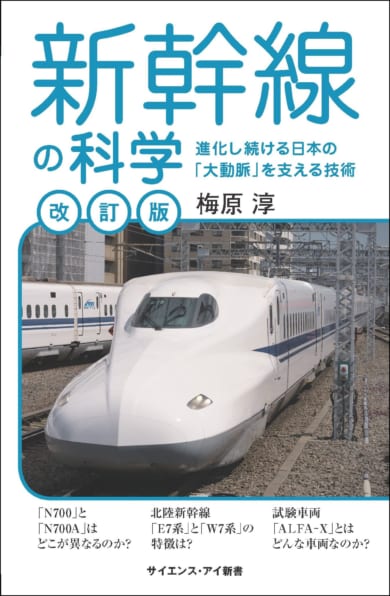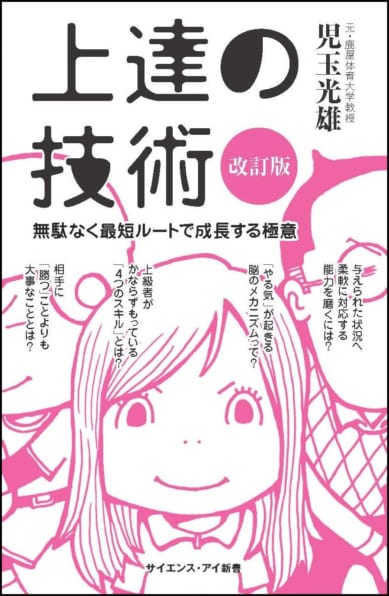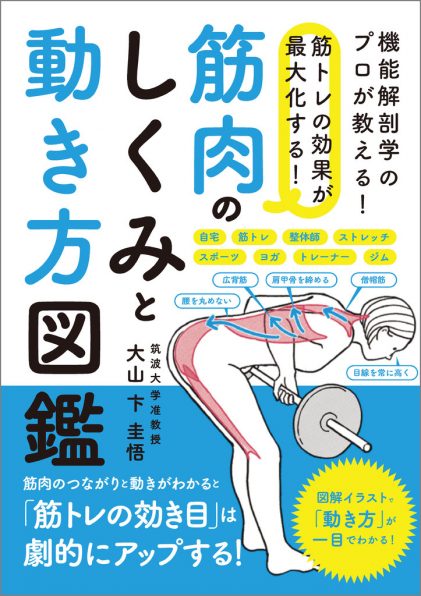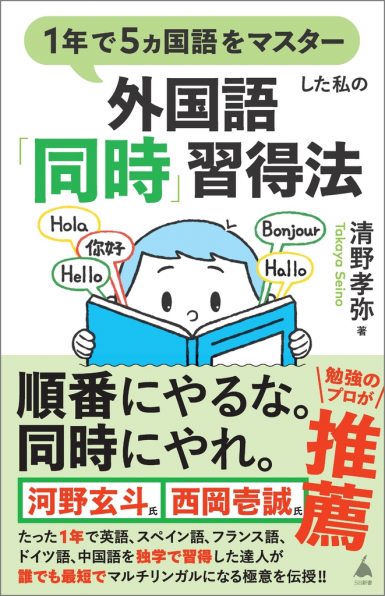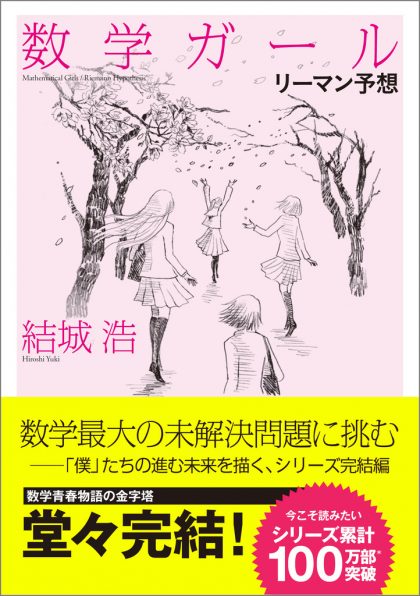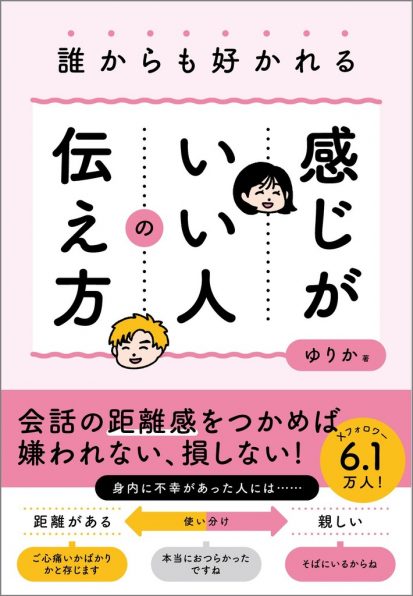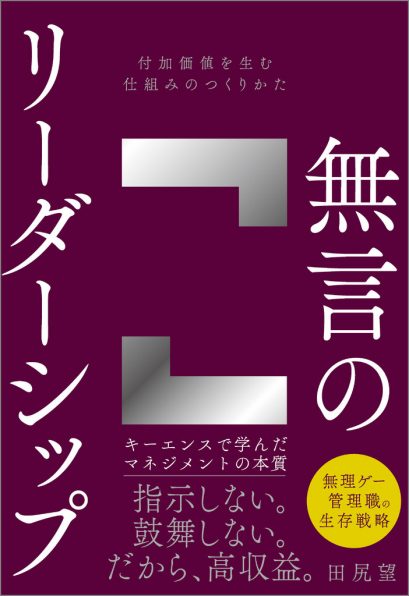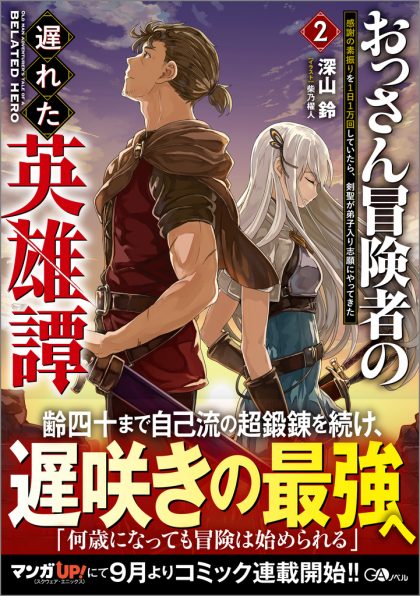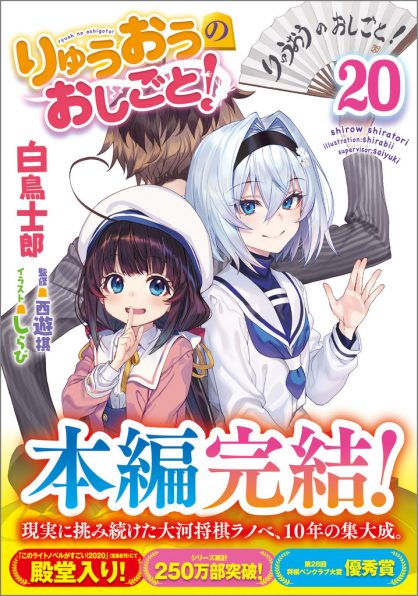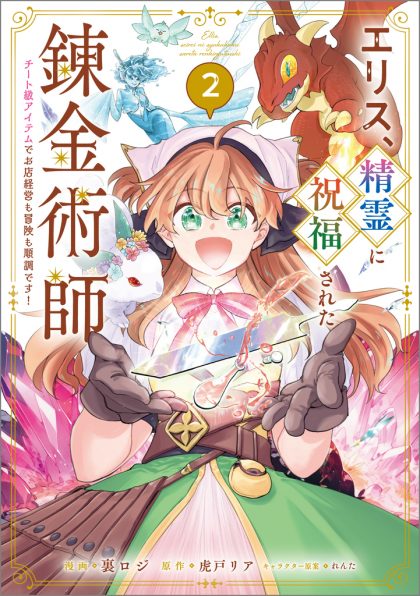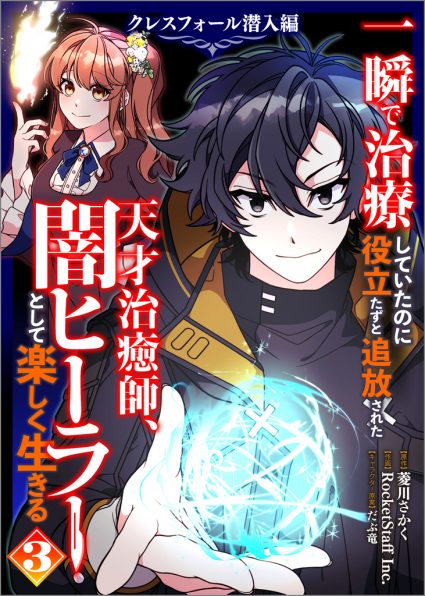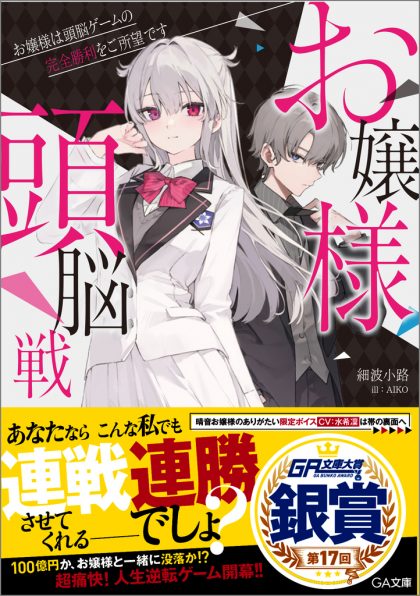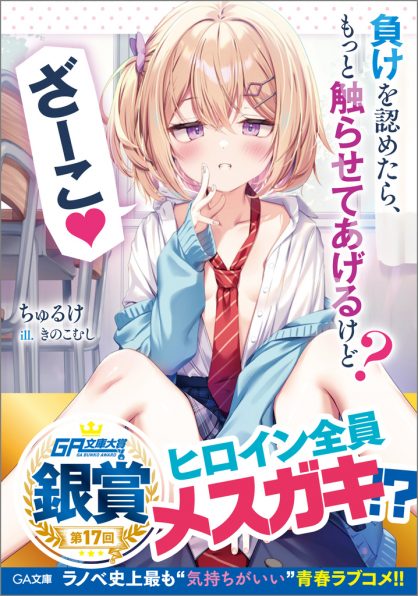[Si新書]僕らのAI論
9名の識者が語る人工知能と「こころ」
AIの「こころ」をテーマに、各界の第一人者が人工知能の今と未来について論じる一冊。
「AIに心は宿るのか?」
「そもそも、心とは何なのか?」
「AIが心を持ったとき、世界はどう変わるのか?」
など、私たちが普段感じている素朴な疑問について掘り下げながら、AIの未来像に迫ります。
■目次:
第1章 AIがヒトになる日 [松原仁]
第2章 人工知能は言葉を話せるか [一倉宏]
第3章 AIでゲームは強くなるのか [伊藤毅志]
第4章 AIは人間を説得できるのか [鳥海不二夫]
第5章 ゲームから現実へ放たれる人工知能 [三宅陽一郎]
第6章 AIは道具であってほしい [糸井重里]
第7章 「生き物らしさ」に必要なのは「痛み」 [近藤那央]
第8章 精神医療にAIを活かす [山登敬之]
第9章 誤解だらけのAI論 [中野信子]